p�l�œǂ݉������v�I��������̔閧�y��������w�E���R�z��Y���m��AI�ް����ݽ�u���z
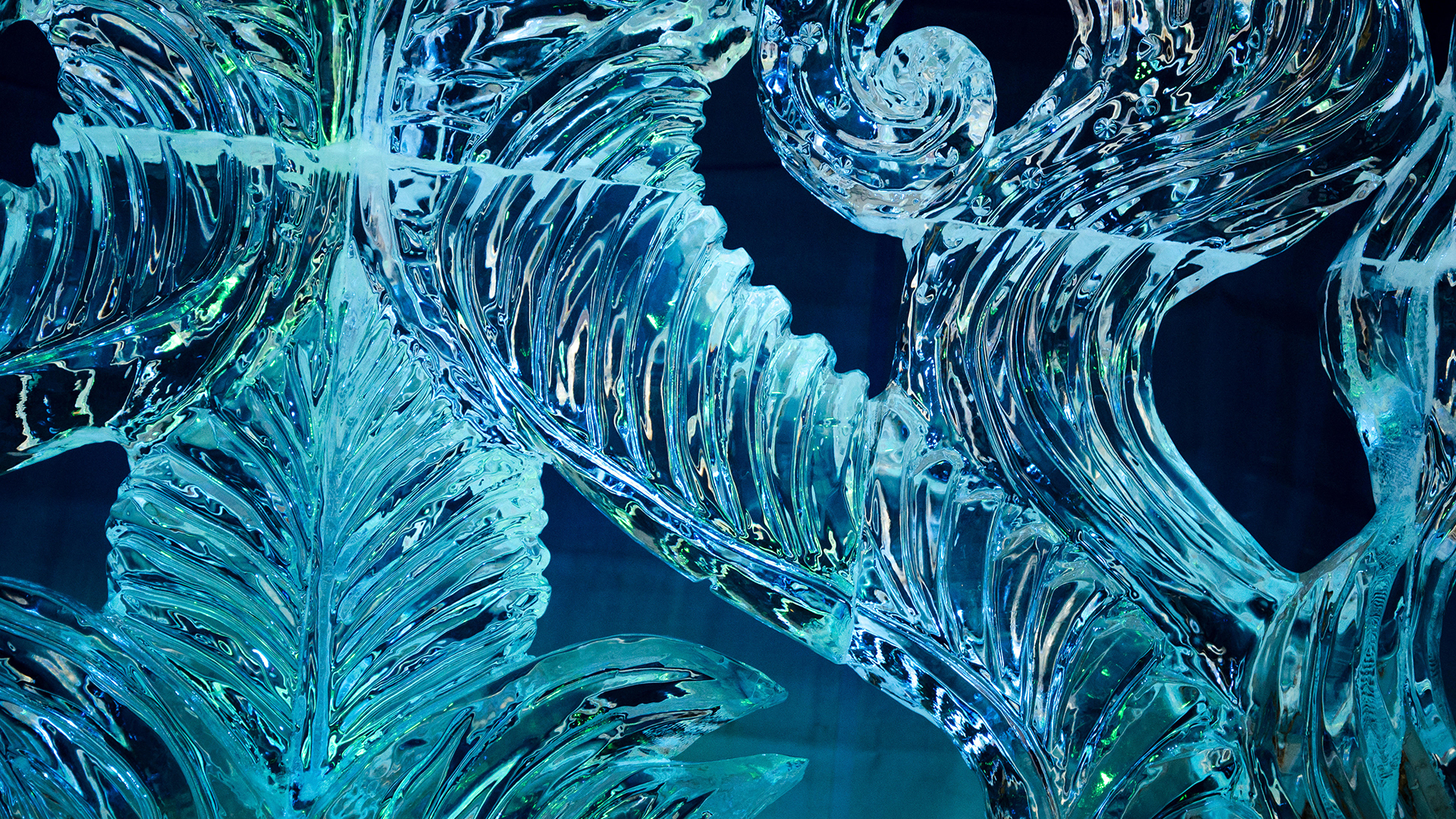
���v�I��������́A���R�̉\�����l�����Ȃ���f�[�^�̈Ӗ���]�������@�ł��B�Ⴆ�A��̌��ʂׂ郉���_���������œ���ꂽ���X�N�������R�̉e���ɂ����̂����������܂��B����Ƃ��Ė�̌��ʂ��Ȃ��i���X�N��=0�j�ꍇ�̃f�[�^���z���R���s���[�^�ŃV�~�����[�V�������A���ۂ̃f�[�^�Ƃ̍��ق�]�����܂��B���̍ۂɌv�Z�����p�l�́A�u���R�ɂ���Ċϑ����ꂽ���X�N���ȏ�̒l���o��m���v�������܂��B�L�Ӑ����i�ʏ�5%�j�ȉ���p�l�Ȃ�A�����������p���A���ʂ�����Ɣ��f���܂��B����A�L�Ӎ����Ȃ��ꍇ�ł��A���������������Ƃ͌������A�����u�A���������Ԉ���Ă���ƌ��_�ł��Ȃ��v�����ł��B���̕��@��p�l�ƗL�Ӑ����Ɋ�Â��A��������]�����邽�߂̕W���I�ȓ��v�I��@�ł��B
![]() ����������������
����������������
�`�����l���o�^�͂�����
���v�I��������̕��@
���܂��܂̉\�����l����
���z�I�ȃ����_���������̗�����Ȃ���l���Ă����܂��傤�B
������ނ����܂Ȃ����ɂ���ė����ɕ��ׂ����邩�ǂ����ׂ郉���_�����Տ��������s�����Ƃ��܂��B
����������A�Q�O�O�l�̐l���Q�����Ă���āA���̂悤�Ȍ��ʂ������܂����B
������݁A���ׂ��������l�@�V�O�l
������݁A���ׂ�����Ȃ������l�@�R�O�l
������܂��A���ׂ��������l�@�U�O�l
������܂��A���ׂ�����Ȃ������l�@�S�O�l
���X�N�����v�Z����ƁA
�V�O�^�P�O�O�|�U�O�^�P�O�O���O�D�P�O
�ƂȂ�܂��B
���āA���̂O�D�P�O�Ƃ������X�N���́A�{���ɖ�Ɍ��ʂ������ďo�Ă������l�Ȃ̂ł��傤���H
����������ƁA�{���͖�̌��ʂ��Ȃ��ă��X�N�����O�̂͂��Ȃ̂ɁA���܂��܋��R���Ċ���t����ꂽ���߂ɏo�Ă������l�Ȃ̂�������܂���B
�������A�ǂ̌Q�ɑ����邩�͒��ׂ悤���Ȃ��̂ŁA���Ċ���t����ꂽ���ǂ����𖾂炩�ɂ���̂͌����I�ɕs�\�ł��B
�����ŁA���C�̗�Ɠ����悤�ɁA��̌��ʂ��܂������Ȃ��i���X�N���̒l���O�j�Ɖ��肵�āA��قǂ̌��ʂ����܂��܋��R�ɐ����Ă��܂����\�����ǂ̂��炢����̂����ׂĂ݂܂��傤�B
�A�������Ƃ������t���g���ƁA�u�A�������i���X�N�����O�j���������ƍl�����Ƃ��ɁA���܂��܂̋��R�̉e���ɂ���āA�f�[�^���琄�肳�ꂽ���X�N���ȏ�ɋɒ[�Ȓl�i0.10�ȏ�̒l�j�������Ă��܂��\�����ǂ̂��炢����̂��v���A���ꂩ�璲�ׂĂ݂悤�Ƃ������Ƃł��B
�V�~�����[�V����
�X��A������ރO���[�v�ł����܂Ȃ��O���[�v�ł��A���傤�NJԂ��Ƃ��āA
�i�V�O�{�U�O�j�^�i�P�O�O�{�P�O�O�j���U�T��
�̊����ŕ��ׂ�����͂����ƍl���܂��B
Type A�`Type D�̐l���������傤�ǔ������ϓ��Ɋ���t����ꂽ�Ƃ�����A������ރO���[�v�P�O�O�l�̂����U�T�l�͕��ׂ�����A�����悤�ɁA������܂Ȃ��O���[�v�P�O�O�l�̂����U�T�l�͕��ׂ�����͂��ł��B
���̂Ƃ��A���X�N���́A
�U�T�^�P�O�O�|�U�T�^�P�O�O���O
�ɂȂ�͂��ł��B
�������A��̌��ʂ��Ȃ������Ƃ��Ă��A���܂��܋��R�̉e���ɂ���āA�Q�̃O���[�v�ԂŃ��X�N�ɍ��������Ă��܂����Ƃ�����܂��B
���̋��R�̉e���ɂ�郊�X�N���̃u�������A�R���s���[�^�[�V�~�����[�V�����Ō��Ă݂邱�Ƃɂ��܂��傤�B
�菇�́A
�@������ރO���[�v�̂P�O�O�l���m���U�T���łP�A�m���R�T���łO���o��悤�ɗ�����������B
�A������܂Ȃ��O���[�v�̂P�O�O�l���m���U�T���łP�A�m���R�T���łO���o��悤�ɗ�����������B
�B�@�ƇA�ŁA�P���u���ׂ��������v�A�O���u����Ȃ������v�ƒu�������āA�O���[�v���Ƃɕ��ׂ�����l���������邩���v�Z���A�������烊�X�N�����v�Z����B
�C�@�`�B�̍�Ƃ��P�O�O�O��J��Ԃ��B
���ʁA���X�N���O�𒆐S�Ƃ������K���z�ɂȂ�܂����B
�������A���X�N���͂O�ɋ߂��Ƃ��낪�R�̒��S�ł����A���傤�ǂO�ɂ͂Ȃ�܂���B
����́A�R�C���g�X���P�O�O�O�ĕ\���o������傤�ǂT�O�O��ɂȂ�Ƃ͌���Ȃ��̂Ɠ��������ł��B
���X�N�����O�D�P�O�ȏ�ɂȂ����̂́A�P�O�O�O�U�Q��ł����B
�{���͍����Ȃ��͂��Ȃ̂ɁA���܂��܂̋��R�̉e���ɂ���ă��X�N�����O�D�P�O�ȏ�ɂȂ��Ă��܂��\�����U�D�Q������Ƃ������Ƃł��B
���āA���̂U�D�Q���Ƃ������l���ǂ��ǂݎ�邩�ł����A���̐��l�̂��Ƃ����l�Ƃ����܂��B
�܂肐�l�Ƃ́A
�A���������������i��r����O���[�v�̃��X�N�ɈႢ���Ȃ��j�ƍl�����Ƃ��ɁA���܂��܂̋��R�̉e���ɂ���āA�f�[�^���琄�肳�ꂽ���X�N���ȏ�ɋɒ[�ȃ��X�N�����v�Z�����\��
�̂��Ƃł��B
���X�N���ł͂Ȃ��āA���X�N��⑼�̌��ʂ̎w�W�ł����Ă��悢�̂ł��B
��قǂ̗�Ō����A
�Б����l���U�D�Q��
�������l���U�D�Q���{�U�D�Q�����P�Q�D�S��
�ƂȂ�܂��B
���̕Б����l�́A�{���͍����Ȃ��͂��Ȃ̂ɁA���܂��܂̋��R�̉e���ɂ���ă��X�N�����O�D�P�O�ȏ�ɂȂ��Ă��܂��\���̂��Ƃł��B
�������l�́A�{���͍����Ȃ��͂��Ȃ̂ɁA���܂��܂̋��R�̉e���ɂ���ă��X�N�����O�D�P�O�ȏ�܂��́[�O�D�P�O�ȉ��ɂȂ��Ă��܂��\���̂��Ƃł��B
�L�Ӑ���
���������l���ƂĂ���������A���X�N�����O���Ɖ��肵���Ƃ��ɁA���܂��܂̋��R�̉e���ɂ���ă��X�N�����O�D�P�O�ȏ�܂��́[�O�D�P�O�ȉ��ƌv�Z����Ă��܂��\�����ƂĂ��Ⴂ�A�ƍl�����܂���ˁB
���Ƃ���A�u�����̃f�[�^�ʼn\���̒Ⴂ���Ƃ����܂��܋N�������v�ƍl������́A�u���X�N�����O���Ƃ�������i�A�������j���Ԉ���Ă���v���Ȃ킿�u���X�N���͂O�ł͂Ȃ��v�i��̌��ʂ͂O�ł͂Ȃ��j�ƍl����������R�ł��B
���ꂪ���v�I��������̗���ł��B
�ł́A���l���ǂ̂��炢��������u���X�N���͂O�ł͂Ȃ��v�ƍl����悢�̂ł��傤���B
���m�ȓ����͂���܂���B
�������A��w�̈�ł́A����I�ɁA�����Η����łT���i�Б��łQ�D�T���j�Ƃ�������p�����Ă��܂��B
�������l���T��������������A�u���X�N���͂O�ł͂Ȃ��v�Ɣ��f���邱�ƂɂȂ�܂��B
�{���̃��X�N���͂O�Ȃ̂ɁA����ă��X�N���͂O�ł͂Ȃ��Ɣ��f���Ă��܂��\�����T�����邱�ƂɂȂ邯��ǂ��A���ꂭ�炢�͋��e���܂��傤�A�Ƃ������Ƃł��B
���̊�l�̂��Ƃ�L�Ӑ����Ƃ����܂��B
���̗�ł́A�L�Ӑ��������T���Ŕ��f����Ƃ������Ƃ́u���X�N�����O���Ɖ��肵���Ƃ��ɁA���܂��܋��R�̉e���ɂ���ă��X�N�����O�D�P�O�ȏ�܂��́[�O�D�P�O�ȉ��Ƃ����\���v�i���l�j���T�������Ȃ�A�܂肽�܂��܂̉\�����T��������������A�u���X�N�����O���Ƃ�������i�A�������j���Ԉ���Ă���v�Ɣ��f���܂��傤�A�Ƃ������Ƃł��B
�����A
���l���L�Ӑ����@�Ȃ�u�L�Ӎ�����v
���l���L�Ӑ����@�Ȃ�u�L�Ӎ��Ȃ��v
�Ƃ��������������܂��B
��قǂ̗�ł́A
�������l���P�Q�D�S�����T��
�Ȃ̂ŁA�u�L�Ӎ��Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�w���@�̌������炢���āA����ꂽ�f�[�^���瓝�v�I����������s�������ʁA�L�Ӎ����������Ƃ��̂݁A�A�������͊Ԉ���Ă���i��r����O���[�v�̃��X�N�ɈႢ������j�ƌ����邱�ƂɂȂ�܂��B
���̑��̂��Ƃ͈�،����Ȃ��̂ł��B
�����A����ꂽ�f�[�^�œ��v�I����������s�������ʁA�L�Ӎ����Ȃ������Ƃ��Ă��A�A�������͐������i��r����O���[�v�̃��X�N�ɈႢ���Ȃ��j�Ƃ͌����Ȃ��̂ł��B
�A���������Ԉ���Ă���Ƃ͌����Ȃ��i��r����O���[�v�̃��X�N�ɈႢ������Ƃ͌����Ȃ��j�ƌ�����݂̂Ȃ̂ł��B
���̂悤�ɁA�A���������Ԉ���Ă��邩�ǂ�����L�Ӑ����Ƃ��l���画�f������@���A���v�I��������ł��B
���v�I��������́A�f�[�^�̔w��ɂ�����ۂ̏𐄑����邽�߂ɁA���R�̉\�����l�����Ȃ��画�f���s����@�ł���A�f�[�^��͂ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ����܂��B���̕��@�̊�{�I�ȍl�������A��̓I�ȗ��p���Đ������܂��B�Ⴆ�A������ׂɌ��ʂ����邩�ǂ����ׂ邽�߂̃����_�����Տ��������s�����Ƃ��܂��傤�B���̎����ł́A200�l���Q�����A������O���[�v�ƈ��܂Ȃ������O���[�v�Ƀ����_���ɕ������܂����B���̌��ʁA�������ŕ��ׂ��������l��70�l�A����Ȃ������l��30�l�A������܂Ȃ������O���[�v�ł͎������l��60�l�A����Ȃ������l��40�l�ł����B���̃f�[�^�����ƂɃ��X�N�����v�Z����ƁA70/100?60/100��0.10�ƂȂ�܂��B�ł́A����0.10�Ƃ������X�N������̌��ʂɂ����̂Ȃ̂��A����Ƃ����R�̉e���Ŕ����������̂Ȃ̂��f����K�v������܂��B���̂悤�ȏꍇ�A���v�I�������肪�p�����܂��B���v�I��������̊�{�I�ȃX�e�b�v�́A�܂��A�������𗧂Ă邱�Ƃ���n�܂�܂��B�����ł́A�A���������u��Ɍ��ʂ͂Ȃ��i���X�N��=0�j�v�Ɖ��肵�܂��B���̉���̂��ƂŁA�ϑ����ꂽ���X�N��0.10�����R�ɂ��\���ׂ܂��B���̂��߂ɃR���s���[�^�[�V�~�����[�V�������s���A��̌��ʂ��{���ɂȂ��ꍇ�ɗ\�z����郊�X�N���̕��z�����܂��B���̃V�~�����[�V�����ł́A������ރO���[�v�ƈ��܂Ȃ��O���[�v�����ꂼ��65%�̊m���ŕ��ׂ�����Ɖ��肵�A������p���ăf�[�^�����܂��B�����āA�e�O���[�v�ŕ��ׂ����銄�����v�Z���A���X�N�������߂��Ƃ�1000��J��Ԃ��܂��B���̌��ʁA���X�N��0�𒆐S�Ƃ������K���z�������܂��B���̕��z����A���X�N����0.10�ȏ�ɂȂ�m�����v�Z�����Ƃ���A���ꂪ1000��62��A���Ȃ킿6.2%�ł����B����6.2%�Ƃ������l��p�l�ɑ������A�u�A���������������ꍇ�ɁA���R�̉e���Ń��X�N����0.10�ȏ�ɂȂ�m���v�������܂��B���ɁA����p�l��p���ċA��������]�����܂��B��ʂɁAp�l�����܂�ɏ������ꍇ�A�A���������������Ɖ��肷��͍̂����I�łȂ��ƍl�����܂��B��w����ł́A����I�ɗL�Ӑ����Ƃ���5%���̗p���邱�Ƃ������A����p�l��5%�����ł���u�A�����������p���A���X�N����0�ł͂Ȃ��v�Ɣ��f���܂��B���̗�ł́A����p�l��12.4%�ł��邽�߁A�A�����������p�����A�u�L�Ӎ��Ȃ��v�ƌ��_�t���܂��B�d�v�Ȃ̂́A�L�Ӎ����Ȃ��ꍇ�ł��A���������������Ƃ͌����Ȃ��_�ł��B���̌��ʂ́u�A���������Ԉ���Ă���ƌ��_�ł��Ȃ��v�Ƃ��������ł���A�A�������̐��������ؖ�������̂ł͂���܂���B���v�I��������́A�f�[�^�Ɋ�Â��ċA���������Ԉ���Ă��邩�ǂ����f������@�ł���A�L�Ӑ�����p�l�����̊�ƂȂ�܂��B���̎�@�𗝉�����ɂ́A�w���@�̊T�O���d�v�ł��B�w���@�Ƃ́A���肪�Ԉ���Ă���ꍇ�ɐ����錋�ʂɊ�Â��āA���̉���̐��ۂf����_���I�ȕ��@�ł��B���v�I��������ł́A�A���������������Ɖ��肵�ăf�[�^����͂��A���̌��ʂ������̃f�[�^�Ɩ������邩�ǂ������������܂��B�����L�Ӎ����F�߂���A�A�����������ł���\���������ƌ��_�t���܂��B�������A���v�I��������̌��ʂ́A�f�[�^�Ɋ�Â����m���I�Ȕ��f�ɉ߂����A100%�̊m�����������̂ł͂���܂���B�܂��A���v�I��������̌��ʂ����߂���ۂɂ́A����ꂽ�f�[�^�������̐v����{���@�ɑ傫���ˑ����邱�Ƃ���������K�v������܂��B�K�ȃ����_������T���v���T�C�Y�̊m�ہA�s�ΐ����m�ۂ��邽�߂̎����v���d�v�ł��B����ɁAp�l�̉��߂ɂ����Ă����ӂ��K�v�ł��B������p�l�͋A���������Ԉ���Ă���\�����������܂����A���ʂ̑傫����Տ��I�Ӌ`��K���������f���Ă���킯�ł͂���܂���B����Ap�l���L�Ӑ������Ă���ꍇ�ł��A�A���������x������؋��ł͂Ȃ��A�P�Ƀf�[�^����A�����������p����\���ȏ؋��������Ȃ������Ƃ��������ł��B���v�I��������́A�f�[�^����ɉ����������邽�߂̋��͂Ȏ�@�ł����A���̌��E��O��������\���ɗ������A�K�ɗ��p���邱�Ƃ����߂��܂��B
�֘A�L��

![]() �y�g�b�v�y�[�W�֖߂�z
�y�g�b�v�y�[�W�֖߂�z![]() �yYouTubeChannel�z
�yYouTubeChannel�z![]() �y���v��͍u�`��b�z
�y���v��͍u�`��b�z![]() �y���v��͍u�`���p�z
�y���v��͍u�`���p�z![]() �yChatGPT�EPython�EExcel�z
�yChatGPT�EPython�EExcel�z![]() �y���ϗʉ�́z
�y���ϗʉ�́z![]() �y��Ó��v��́z
�y��Ó��v��́z









