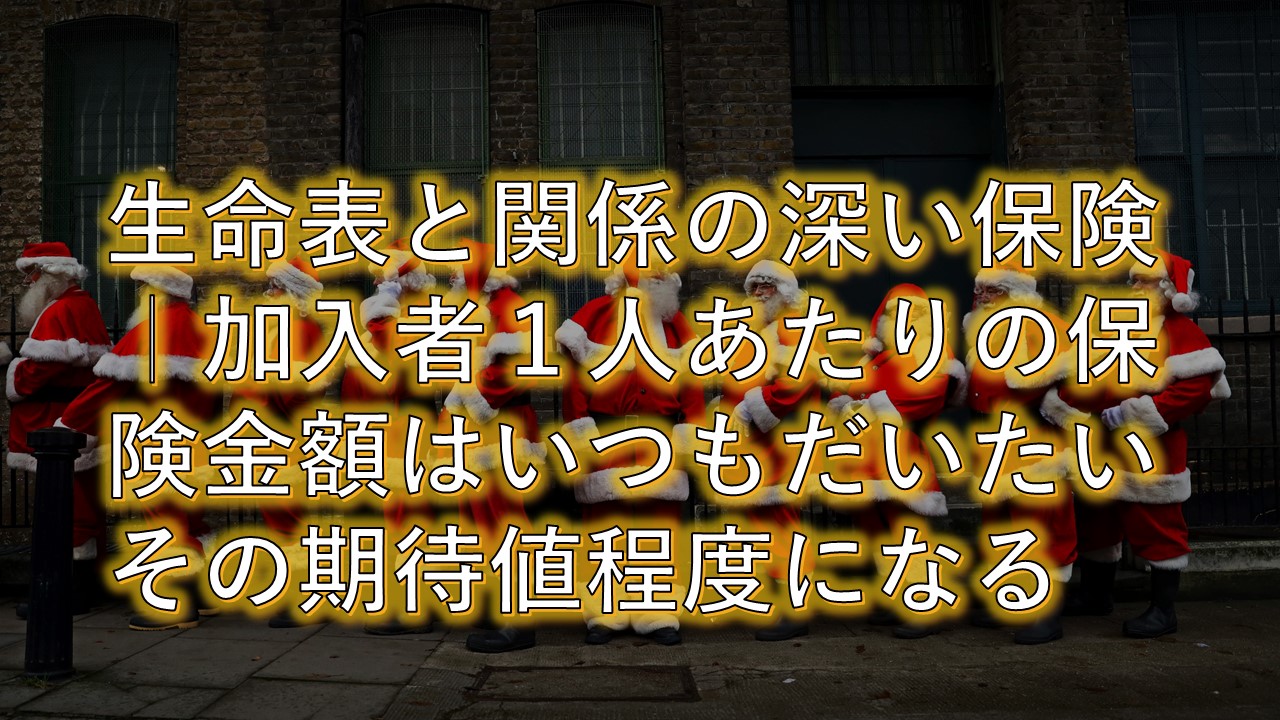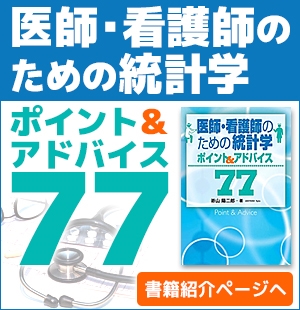保険金額の謎解き!期待値が導く安定経営の秘密【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】
保険加入者1人あたりの保険金額は、期待値程度になることが一般的です。これは、生命表を使用して将来支払わなければならない保険金の期待値を推定し、それに基づき保険料率を決定することにより達成されます。加入者数が増えるにつれて、1人あたりの保険金額が期待値から大きく逸脱する確率は低下し(大数の法則)、保険会社は安定した経営を続けることが可能となります。これは、個々の加入者にとっては小さなリスク(例えば事故にあう確率)を、多くの加入者が共有することにより、大きな保険金支払いのリスクを分散できるという保険の基本原理に基づきます。ただし、加入者間でのリスクが独立していない場合(例:地震)、大数の法則は成り立たず、保険会社の経営に影響を及ぼす可能性があります。
![]() ▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼
チャンネル登録はこちら
生命表と関係の深い保険
生命表と関係の深い保険のしくみを考えます。
生命表と直接関連しているのは生命保険ですが、その前に損害保険のしくみを考えてみましょう。
損害保険は、保険会社が加入者から少しずつ保険料を集めます。
契約期間中に事故にあった加入者には、保険料に比べはるかに多額の保険金が支払われます。
一方、契約期間中に事故にあわず無事に過ごした人は、いわゆる掛け捨てで、保険料を払っただけで何ももらえません。
加入者が事故にあうかどうかは偶然に左右されますから、ある期間内(たとえば1年間)に支払わなければならない保険金額も偶然に左右されます。
にもかかわらず、保険会社は、常にほぼ一定の保険料を受け取って経営を続けています。
どうしてそういうことができるのでしょう。
仮に、ある保険会社に保険加入者がひとりしかいないとしましょう。
ひとりの保険加入者が事故にあうかどうかは偶然に左右されますから、そのひとりに1年間に支払わなければならない保険金の額は、確率変数と考えることができます。
そこで、この加入者がもらう保険金額の期待値を考えてみます。
確率変数の期待値とは、確率変数の値の、すべての可能性にわたった平均です。
普通は、事故にあう確率は小さいですから、保険金額は、ほとんどの可能性で0、ごくまれに大きな額となり、保険金額の期待値はそれほど大きくありません。
たとえば、加入者に1年間に事故にあう確率が1%であるとし、事故にあったときには100万円支払う契約だとすると、
1年間に加入者1人あたりに保険会社が支払う保険金の期待値は、
100万円×0.01+0円×(1−0.01)
で、1万円です。
しかし、だからといって保険会社が保険料を1万円しか受け取っていなかったとしたら、事故のときに100万円の保険金を支払うことができません。
たったひとりの加入者については、期待値は現実のものではないのです。
ところが、保険加入者が10万人いて、それぞれが独立に1%の確率で事故にあうとしましょう。
そうすると、10万人の加入者全員が同時に事故にあうとしましょう。
そうすると、10万人の加入者全員が同時に事故にあうなどという事態はまず起こりえず、たいてい10万人の1%の1000人程度が事故にあう、ということが経験的にわかります。
このとき、事故にあった1000人に100万円ずつ保険金を支払うとすると合計は10億円ですから、10万人の加入者1人あたりにすると1万円になります。
つまり、1年間の加入者1人あたりの保険金額はいつもだいたいその期待値程度になり、期待値が現実のものになるのです。
このことを統計学的にいうと、1年間の加入者1人あたりの保険金額が期待値から大きくはずれる確率は、加入者が多くなるほどゼロに近づくということができます。
これを大数の法則といいます。
加入者1人あたりの保険金額は期待値程度
つまり、たくさんの加入者が独立に事故にあうのならば、保険金額の期待値(+保険会社経営のための費用+保険会社の利益)程度の保険料を各加入者から受け取っておけば、事故のときに保険金を支払うことができるというわけです。
このように、各個人にとって小さな確率(1%)で起きる大きな損害(100万円)のリスクを、独立な個人がたくさん保険に加入することによって、
期待値程度の保険料(100万円×1%=1万円)の確実な支払いと交換できるというのが保険のしくみです。
したがって、自分は事故にあわないから保険料は払いたくないと言っては、保険は成り立ちません。
自分の払った保険料が他人への保険金に使われるのを承知するかわりに、自分が万一、事故にあったときには、自分の払った保険料より多額の保険金をもらえるわけです。
ただ、保険金の期待値の大きい人のグループと小さい人のグループに分けて、保険料に差をつける、ということは行われています。
たとえば、年間の走行距離の少ない人は保険料が安い自動車損害保険などのリスク細分型保険は、事故の危険が大きい、つまり、保険金の期待値が大きい人から高い保険料をとるかわりに、期待値の小さい人からの保険料を安くする方法です。
一方、生命保険においては、保険会社は加入者から掛け金を受け取り、加入者が死亡したとき保険料を支払います。
しかし、それぞれの加入者がいつ死亡するかはわかりませんから、多額の保険金を突然支払うことになります。
ただ、保険加入者がたくさんいてそれぞれが独立に死亡するならば、大数の法則にしたがって、つねにほぼ期待値どおりの数の人が死亡すると考えられます。
ですから、将来支払わなければならない保険金の期待値を推定すれば、それをもとに保険料率を決めて保険商品を企画することができます。
この推定には生命表が使われます。
ところで、事故にあったり、死亡したりすることが独立でない場合はどうなるのでしょうか。
一番わかりやすい例が、地震災害の場合です。
地震のときは、その地域の保険加入者が同時に事故にあったり、死亡したりするわけです。
したがって、上の「それぞれの加入者が独立に事故にあう」「それぞれの加入者が独立に死亡する」という前提が成り立たず、
大数の法則が成り立ちません。
この場合、その地域の加入者が同時に保険料を請求するわけですから、各加入者の保険金額の期待値程度の保険料を受け取っていては保険金が支払えず、保険会社は破産してしまいます。
つまり、保険は「誰でもあう可能性のある危険」に対する助けにはなりますが、予想外の事態には弱いということがわかります。
2001年の米国同時多発テロ事件では、保険金の支払いのために破綻した保険会社がありました。
百階建てのビルが2つ、一度に全壊するということは、誰も想像できなかったことです。
なお、世の中に見られる大数の法則の例としては、保険の例のほかに、電話や銀行預金があります。
ある地域の電話の利用者が、互いに独立に電話をかけるかぎりは、同時に通話される量は、大数の法則によってだいたい期待値どおりになります。
したがって、電話交換機の処理能力は、その期待値にいくぶんの余裕をもたせて作られています。
そのため、独立でない場合、たとえば、大災害が起きて人びとがいっせいに安否確認の電話をする場合は、交換機の処理能力を超えて、電話がかかりにくくなります。
また、銀行の普通預金は、いつでも好きなときにお金をひき出すことができます。
預金者が互いに独立に預金をひき出すかぎりは、ある銀行から1日にひき出される金額の合計は、大数の法則によってだいたい期待値どおりになります。
したがって、銀行ではそれに見合った現金を用意しておけばよいわけです。
しかし、たとえば「あの銀行がつぶれそうだ」という噂が流れて、預金者が一斉に預金をひき出そうとすると、そんなお金は銀行にはないので、ほんとうに銀行がつぶれてしまいます。
過去には、電車内で誰かが冗談で、「あの銀行、大丈夫?」と言ったのが広まって、その銀行に預金をひき出しに来たお客が殺到して大騒ぎになったことがあります。
関連リンク