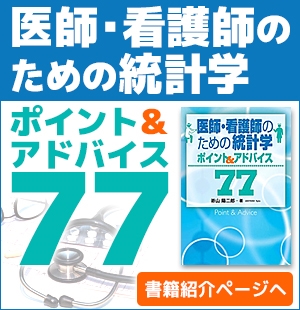赤信号右折が招いた統計的誤算と安全性の真実【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】

1970年代、米国では赤信号での右折が許可され始めたが、当初は安全上の懸念が指摘されていた。石油危機を契機に燃料節約のため導入が進み、連邦議会も推進したが、その安全性に関する研究は検定力が不十分で、統計的に有意な差がないことを理由に安全性への影響が軽視された。一方で、後年のデータから衝突事故が20%、歩行者事故が60%、自転車事故が2倍に増加していたことが明らかになった。この例は、統計的有意性だけに依存する判断の危険性を示し、2002年の舗装路肩の研究でも同様の誤りが繰り返された。舗装路肩が事故率を減少させる傾向が示唆されたにもかかわらず、有意でない差を根拠に費用便益分析が行われず、安全性の向上効果が正当に評価されなかった。信頼区間を用いた分析の必要性が強調されるべき事例である。
![]() ▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼
チャンネル登録はこちら
赤信号での誤った方向転換
1970年代,米国の多くの地域で,運転手に対して赤信号で右折することが許可されはじめた。
それに先立つ長い間、道路の設計者と土木技師は,赤信号での右折を許可すると衝突や歩行者の死亡が増えるので,安全上の問題があると主張してきた。
しかし. 1973年の石油危機とその影響により,交通部門は,通勤者が赤信号を待つ際に無駄となる燃料を節約できるように赤信号での右折を許可すべきだと考えるようになった。
そして,ついに米国の連邦議会は,各州に対して赤信号での右折を許可するように求めた。
赤信号での右折を,建物の断熱基準や効率的な照明と同様にエネルギー節約の措置として扱ったのだ。
この変化が安全に対して与える影響を考察する研究がいくつか行われた。
そうした研究の1つに,バージニア州の高速道路・交通部門のコンサルタントが実施した研究がある。
この研究では,赤信号での右折が許可されるようになった交差点20か所について,変化前と変化後の違いが調査された。
変化前は,これらの交差点で事故が308回あった。
変化後は,同等の長さの期間で事故が337回あった。
しかし,コンサルタントは、この差は統計的に有意ではないと報告で述べた。
この報告が知事に送られた際,高速道路・交通部門の長は,赤信号での右折の「実施以降,運転手や歩行者に対する意味のある危険は認められておりません」と記した。
つまり。統計的に有意でないということを現実に意味がないということに転換してしまったのだ。
これに続くいくつかの研究も同じような結果だった。
すなわち,衝突回数は少し増加するが,こうした増加が統計的に有意なものだと結論づけるにはデータが十分でないというものだ。
ある報告は以下のような結論を述べている。
〔赤信号での右折の〕採用以降,右折が関わる歩行者事故が増加したと疑う理由はない。
もちろん,こうした研究は検定力が足りなかったのだ。
しかしながら,さらに多くの市や州が赤信号での右折を許可するようになり,米国全体で広く行われるようになった。
より有用なデータセットを作るために,これら多数の小規模な研究を統合しようとした人は、どうもまったくいなかったようだ。
その間,ますます多くの歩行者が轢かれ,ますます多くの車が衝突にまきこまれた。
数年後に,右折が関わる事故について,衝突が20%増加し,歩行者が轢かれることが60%増加し,自転車に乗っている人がぶつけられることが2倍になったという明確な結果が最終的にもたらされるまでは,このことを確信を持って示すために十分なデータを誰も集めることができなかった。
ああ,交通安全の業界はこの例からほとんど学習していない。
例えば, 2002年のある研究では,舗装路肩が田舎の道路での交通事故率に与える影響を考察している。
当然のことながら,舗装路肩は事故のリスクを減らす。
だが,この減少が統計的に有意だと明言するためのデータは十分になかった。
このため,この研究の著者は,舗装路肩の費用は正当化されないと述べた。
有意でない差について,差がまったくないことを示しているかのように扱ったために,費用便益分析を行わなかった。
集めたデータが舗装路肩によって安全性が向上するということを示唆しているにもかかわらずだ。
証拠は,期待していたp値の閾値に見合うほど強いものでなかったのだ。
より良い分析をしていれば,路肩が便益をまったくもたらさない可能性はあるかもしれないが,データは路肩が実質的な便益をもたらすこととも矛盾しないと認めていただろう。
このことは,信頼区間を見ることを意味する。
1970年代、米国では赤信号での右折が許可され始めました。当初、この制度変更には安全上の懸念があり、議論が繰り広げられましたが、石油危機を契機に燃料消費を削減する取り組みの一環として多くの州で導入が進められました。連邦議会もこの動きを後押しし、赤信号での右折を推奨する政策を実施しました。しかし、この制度が導入される際、安全性に関する研究が行われたものの、その多くは十分な検定力を持たないものでした。これにより、赤信号での右折が交通事故に及ぼす影響に関するデータの分析結果は、統計的に有意な差がないことを理由に安全性への影響が軽視されました。当時、統計学的有意性が政策決定の主要な基準とされていたため、有意差が観察されなかったという結果は「安全性に問題はない」という結論として解釈されました。しかし後年のデータから、この政策変更により実際には事故件数が増加していたことが明らかになりました。具体的には、交差点での衝突事故が20%増加し、歩行者事故は60%、自転車事故は2倍に増加していたという結果が報告されました。この事例は、統計的有意性のみに依存して政策を決定することの危険性を示す典型的な例として知られています。この問題は単に赤信号での右折にとどまらず、統計分析の結果をどのように解釈し、実際の政策に反映させるべきかという統計学や政策科学における重要な教訓を提供しています。さらに、この問題は2002年に行われた舗装路肩の研究においても類似の形で繰り返されました。この研究では、舗装された路肩が交通事故の発生率を減少させる可能性を示唆する結果が得られましたが、有意差が観察されなかったため、費用便益分析が行われず、舗装路肩が安全性の向上に寄与する可能性が過小評価されました。このように、統計的有意性に過度に依存することで、本来評価されるべき重要な効果が見落とされるリスクが存在します。これらの事例は、政策立案において統計学的手法の限界を認識し、信頼区間や効果サイズなど、より包括的な評価基準を採用する必要性を浮き彫りにしています。特に、赤信号での右折の事例においては、統計的有意性の枠を超えて、信頼区間を活用した分析やシミュレーション手法を用いることで、より正確な安全性評価が可能であったと考えられます。同様に、舗装路肩の研究では、信頼区間を用いて結果の解釈を拡張することにより、政策決定者により説得力のあるデータを提供することができたはずです。これらの教訓から、政策立案やインフラ整備に関わる研究では、統計的有意性だけでなく、信頼区間や効果の実際の大きさ、さらにそれが社会全体に与える潜在的影響を総合的に考慮することが求められます。このような観点を持つことで、統計データの解釈がより正確になり、政策の有効性や安全性が向上すると期待されます。さらに、このような教訓は統計教育や研究者の育成にも影響を与え、より多様な分析視点を持った人材の育成が進むことで、統計学と社会との接点がより強固なものになるでしょう。このように、赤信号での右折と舗装路肩の事例は、統計的有意性の枠を超えた政策評価の重要性を強調するとともに、未来の政策立案に向けた貴重な指針を提供しています。
関連記事