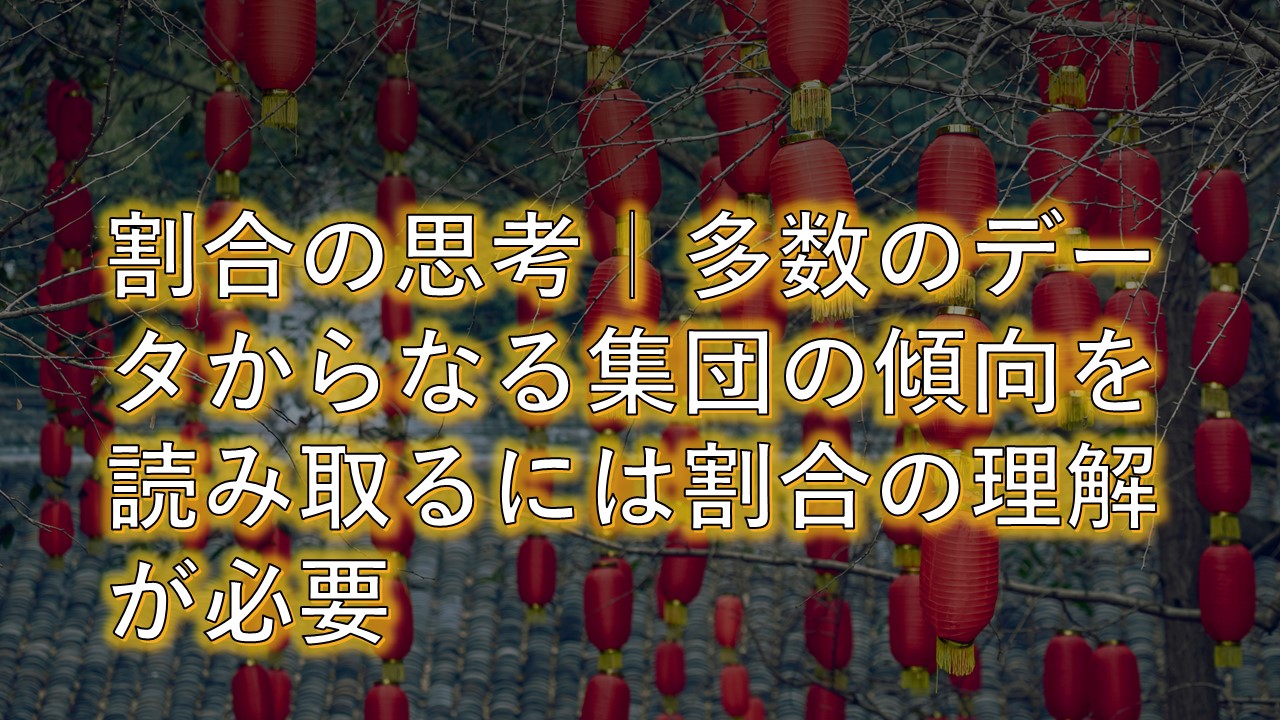割合で見る世界: 恐怖を解消する統計学の力【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】
ものごとを割合で理解し、表現することの重要性を強調しています。例えば、ハレー彗星の接近時に流れた過剰反応や、2011年の大震災後の放射線に関する誤解を通して、正確な割合の理解がなければ不必要な恐怖や混乱を生むことを示しています。統計学では、集団の傾向を「何人」という絶対数ではなく、「何%」という割合で捉えることで、その情報の意味を適切に理解することが強調されています。このアプローチは、情報がどの程度の重要性を持つのかを正しく評価するために不可欠です。
![]() ▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼
チャンネル登録はこちら
割合の思考
100年前にハレー彗星が接近したとき、彗星の尾に青酸が含まれることがわかり、さらにその尾と地球が交差することがわかりました。
このため、「青酸ガスのために人類はみな死んでしまう」という噂が流れ、自転車のチューブの先に空気を貯めておいて尾が通過する間に吸おうとした人々や、桶の水に顔をつけて息を止める練習をした人々がいたそうです。
もちろん、彗星のガスは地球の大気よりはるかに薄いので、何も影響はありませんでした。
いまの私たちは、当時の人々を笑えるでしょうか。
2011年の大震災にともなう原発事故で、放射線に関する報道が多数ありました。
このちき、なかには説明が不正確なために、混乱を招いたものがありました。
たとえば、「沖縄でも480万ベクレルの放射性ヨウ素を検出」という記事をみて大騒ぎしている人がいましたが、これは「1平方キロメートル当たり」480万ベクレルでした。
1平方メートル当たりなり4.8ベクレルです。一方、人体はつねに4000ベクレル程度の放射性物質を含んでいます。
また「マイクロシーベルト」と「マイクロシーベルト毎時」がきちんと区別されないために意味が不明になってしまった報道がありました。
さらに、「原発近くで○ミリシーベルト毎時の放射線を検出、これは1時間浴び続けるとレントゲン写真△枚分の被爆に相当・・・」と報じられると、実際にレントゲン写真△枚分の放射線を浴びたと思ってしまう人がいます。
実際には、○ミリシーベルト毎時の放射線は一瞬出ていただけかもしれず、実際にレントゲン写真△枚分の放射線を浴びるのとは違います。
多数のデータからなる集団の傾向を読み取る
これらの例は、ものごとを割合でとらえること、割合で表されたものごとの意味を理解することの重要さを示しています。
統計学は、多数のデータからなる集団があるときに、たとえば「身長○cm以上の人が何%」のように、その集団の傾向を読み取るために用いられます。
このとき、「身長○cm以上の人が何人」という表現では全体の人数がわからないかぎり、それが多いのか少ないのかを読み取ることはできません。
ですから、つねに「身長○cm以上の人が何%」という割合で理解する必要があります。
関連リンク