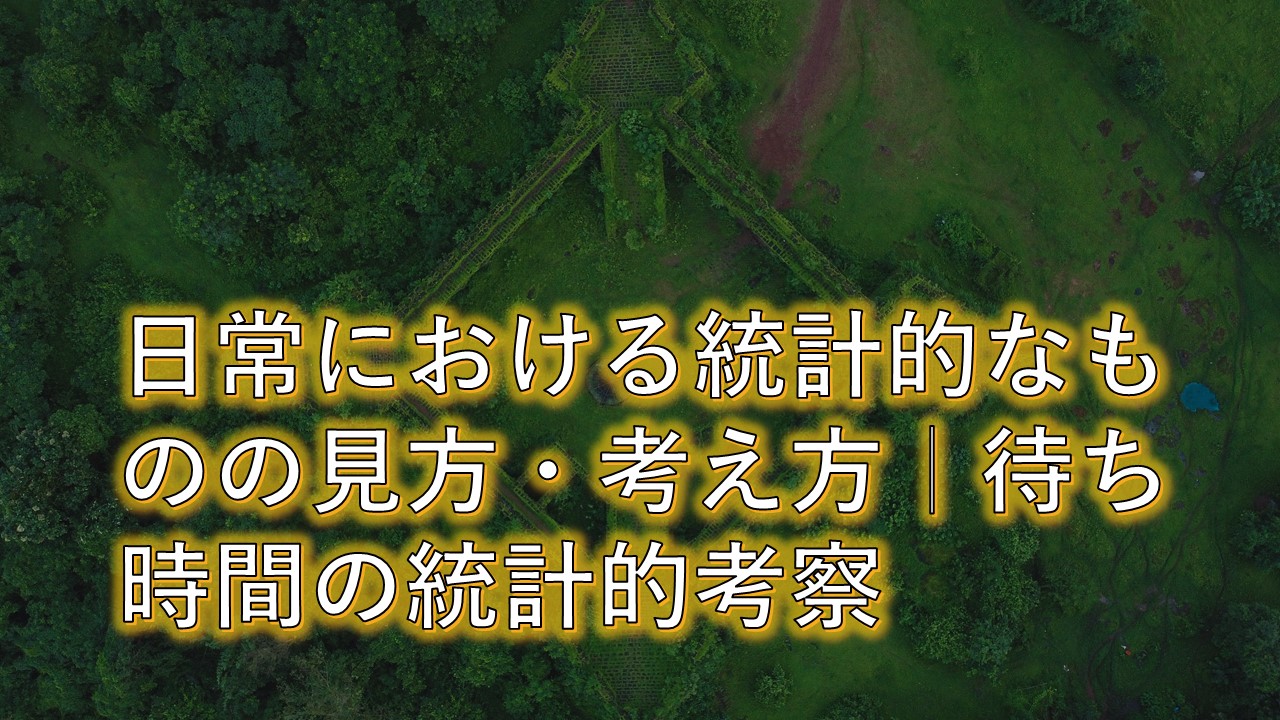無意識の中の統計学: 日常を数値で読み解く【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】
人々は日常生活で、統計的考え方を無意識に使っています。例えば、恋人との待ち合わせでは、過去の経験に基づいて待つべき時間を統計的に判断します。集会の開始時刻を決める際にも、司会者は参加者の集まり具合を観察し、過去の事例を参考にして待ち時間を統計的に考慮します。これらの判断は、正式に統計学を学んでいなくても行われます。日常のさまざまな場面で、人々は過去の経験を無意識に集計し、それを基に判断を下しています。これは、見えないパソコンが頭の中で動作しているかのように、経験を統計的に処理していることを示しています。
![]() ▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼
チャンネル登録はこちら
日常における統計的なものの見方・考え方
一般の人々でも、日常、知らないうちに統計的なものの見方なり考え方なりをしています。
恋人と待ち合わせている若い人たちは、約束の時間が過ぎたあと、「いつまで待たせる気なんだろう」とブツブツ言いながらも、どれくらいの時間の範囲でじっと待つべきかを、統計的に判断しています。
これまで何度かの事例を繰り返し、反復に基づいてです。
もちろん彼または彼女が統計学を正規に学んでいなくともそうしています。
集会の出席者を待つ場合もそうです。
待ち時間の統計的考察
通達した集会開始時刻からどれだけ待つべきかを、司会者は刻々の集まり具合を観察し、それから判断して決めます。
「まだお見えにならない方がいらっしゃるようですが、定刻の時間もだいぶ過ぎたことですし・・・・」というときの司会者の頭の中では、
これまでの事例と集団の習性に関する、統計学的考察ともいうべきものが働いているにちがいありません。
もちろんそれは目に見えるものではないですし、本人もとくに意識していないでしょうが、結構、複雑な推論をめぐらせているにちがいありません。
車に危うくひかれそうになったときの体験は、いつまでたっても、まったくそのままアリアリと思い出せるでしょう。
原情報のままで、脳細胞の中にメモリーとして貯えられてきているわけです。
しかし、あの世行きにつながらない、ヒャッとした程度のちょっとした危険には始終出くわしていて、いちいちおぼえてはいません。
もちろん完全に忘れ去っているかというと、そうでもありません。
それらはある種の情報処理によって学習効果としてまとめられ、統計的な形に変換されたメモリーとして生きているように思われます。
頭の中の、見えないパソコンが事例データを無意識に集計し、その結果をやはり無意識に検索しているのです。
関連リンク