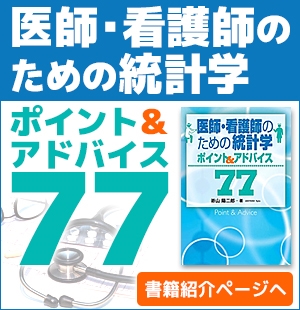統計学で解き明かす不確実性と母集団の推定【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】

不確実性は自然科学や社会科学を問わず重要な概念であり、統計学や数学的手法が不可欠です。母集団全体を調査するのは現実的ではないため、標本を用いて推定を行いますが、標本は母集団の一部であるため誤差や不確実性が生じます。統計学はこの不確実性を扱う手段であり、標本の平均や標準偏差を用いて母集団のパラメータを推測します。また、仮説検定によって標本間の差が偶然かどうかを判断し、相関や回帰分析により変数間の関係性を探りますが、相関は因果関係を証明するものではありません。
![]() ▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼
チャンネル登録はこちら
不確実性
自然科学、社会科学の分野を問わず、あらゆる分野において、「不確実性」について扱うことが不可欠となっています。
たとえば、日本人の意識調査を行う場合、分析対象とする集団全体を母集団と呼びますが、この場合、日本人全体が母集団となります。
しかしながら、母集団全体について知ることは、多くの場合困難です。
全員を調査するとなると小さな子供ま除いても1億人程度を調査する必要があることになります。
このような場合、母集団からその一部を選び出し、選び出された集団について調査を行い、母集団について推定するということが行われます。
母集団から選び出されたものを標本(sample)、選び出すことを標本抽出と呼びます。新聞社やテレビ局が行う世論調査では、通常、数千人程度を選び、面接や電話などによる調査を行って結果を集計しています。
しかしながら、標本は母集団のごく一部です。標本が母集団をよく表しているかどうかは、どのような標本を抽出するかに依存し、不確実性やばらつきの問題を生じます。
母集団を1億人として、標本を1,000人抽出したとすると、10万分の1を調査したにすぎないし、大規模な調査を行って1万人をちょうさしても1万分の1を調査したにすぎません。
私たちが調査するのは標本ですが、知りたいのはあくまでも母集団についてです。
また、ファイナンスの分野では、将来の不確実性を扱いますし、量子力学などでは、電子の挙動はすべて不確実性を伴っています。
このような不確実性やばらつきに対応するためには、数学的な道具として、どうしても確率や確率分布、確率変数の基礎的な知識が必要となります。
不確実性と統計学
統計学は不確実性のもとで結論を引き出す一つの手段です。
それによって、小さなグループ(標本)についての知識を数値化し、より大きなグループ(母集団)へと一般化を試みる際、そこのどの程度の誤差が含まれるかを評価し、認識することが可能になります。
統計解析はまず標本の記述からはじまります。
図を描いてみることは、標本を記述したりその他の分布と比較したりする場合に、非常に有効な方法であることがわかります。
しかし、私たちにとってさらに興味深いのは、標本の中心化の傾向を表す尺度や、そのばらつき具合を表す尺度を得ることです。
こういった尺度(量的変数の)の中で最も重要なものは、算術平均と標準偏差です。
これらは特に正規分布、すなわち左右対称でつりがねのような形をした分布曲線を定義する場合に重要です。
ひとたび平均と標準偏差が得られたならば、Z単位を用いて、2つの異なる分布からとられた値を比較することもできますし、また、観測値の何パーセントが、その変量のさまざまな値の上下に現れるかを推定することもできます。
さらには、標本から作られた統計量に基づき、母集団のパラメータを推測することも可能です。
すなわち標準偏差という概念によって、母集団の真の値(たとえば平均や比率の値)が含まれると考えられる信頼区間を決定することができます。
通常は、真の値の存在に95%確信がもてるような範囲や、99%確信がもてるような範囲が用いられます。
同様な原理に基づき、二つ(あるいはそれ以上)の標本を比較し、それらが同一の母集団からとられたものとみなしうるほど似ているか、を問題にすることができます。
それらの間の差は、母集団における本当の差を示唆するほど大きいものでしょうか。
とすれば、今後同様な方法で一対の標本を選べば、そこにおいてもこのような差はくり返されることになります。
そこで、その標本が同一の母集団からとられたものであり、その差は純粋に偶然だけから生じたものであるという帰無仮説を立てます。
そして検定を行うことにより、この仮説の起こりやすさを判断することができます。
それほど差の大きな二つの標本が一つの母集団から得られる確率が5%より小さいことが判明したならば、その仮説は棄却してもよいことになります。
より注意深くありたいと思うならば、同一の母集団から得られる確率が1%以下であるほど差が大きくないかぎり、その帰無仮説を棄却しない(その差を本当の差とは認めない)ことにすればよいのです。
仮説が棄却されるような差は有意であるといわれています。たとえそれが実際的な意味で何ら重要でなくともよいのです。
複数個の標本のいずれかに有意な差があるか否かを決定するための検定も存在しますが、それは分散分析であり、グループ間の分散とグループ内の分散を比較します。
量的変数ではなく、質的な変数を扱う場合、二つの標本間の平均の差に代わって、比率に有意な差があるかどうかを問うことになります。
その場合には、カイ2乗検定と呼ばれるノンパラメトリックな検定が用いられます。
これは、偶然だけにより期待される観測値の頻度と実際に現れる頻度とを比較するものです。
こういったノンパラメトリックな手法は、質的変数を扱う場合には不可欠ですが、それ以外にも母集団が正規分布に従っているか否かが確かでない場合にも薦められます。
最後に、互いに関連のある2つの変数についての標本が対になって得られた場合、それらの関係に興味をもつことが多いです(たとえば人の身長と体重の関係など)。
相関とは、このような関係を測るためのもので、相関係数によってその強さを表します。
相関係数はー1から1までの間の値をとります。
散布図は相関を表すのに最も有用な方法ですが、標本の中のいくつかの個体が等しい値をとるような場合には、散布図のかわりにある種の表を用いる必要があります。
回帰分析では、標本にみられた関係を用いて、母集団において一方の変数の値が得られた場合に、それに対応する他方の変数の値を予測することができます。
こういった予測は、相関の強さが増すにつれて正確になると考えられます。
ただし、相関がきわめて強く、予測が正確であったとしても、その事実から、一方の変数が他方により引き起こされているという因果関係を証明することはできません。
たとえ因果関係の存在が理屈に合っていたにしても、相関があることと因果関係があることは異なります。
相関がみられるのは、変数Xが変数Yを引き起こしているかもしれませんし、あるいはその反対かもしれません。
あるいは、XもYも共に他の変数Zにより決定されているためかもしれません。さらには、その関係は偶然のもたらした結果かもしれません。
統計学は、これらのストーリーに沿った推論に対して、データがそれを支持したり否定したりします。しかし、絶対的な証明は不可能です。
不確実性という概念は、自然科学や社会科学を問わず、さまざまな分野で極めて重要な役割を果たしています。私たちが何かを研究する際、その結果には必ず不確実性が伴います。この不確実性は、調査や実験、観測の過程において、予期しないばらつきや誤差が発生するためです。不確実性を考慮せずに得られた結果を信じ込むことは、誤った結論を導く可能性があります。したがって、研究者や科学者は常にこの不確実性をどう扱うかを考える必要があります。不確実性の問題は、特に統計学において重要です。統計学は、データを分析し、結論を導くための方法論を提供しますが、その基礎には不確実性を前提とした考え方が組み込まれています。たとえば、ある日本人の意識調査を行う場合、調査対象となる集団全体を「母集団」と呼びます。この場合、日本人全体が母集団となりますが、日本人全体について知ることは現実的に非常に困難です。日本の総人口は約1億人に達しますが、そのすべてを調査することは、時間的にも経済的にも不可能に近い作業です。そこで、母集団全体ではなく、その一部を抽出し、その標本について調査を行うことで、母集団全体を推定するという手法が一般的に採用されています。このプロセスを「標本抽出」と呼びます。標本は母集団を代表する一部のグループですが、ここで問題になるのは、この標本がどの程度母集団全体を正確に表しているかということです。母集団を十分に代表していない標本から得られた結論は、誤りを含む可能性が高くなります。たとえば、日本の人口を1億人とし、その中から1,000人を標本として抽出する場合、これは母集団全体のわずか10万分の1に相当します。仮に1万人を調査したとしても、それは母集団の1万分の1にすぎません。このように、標本が母集団全体を正確に反映しているかどうかには常に疑問が残ります。このため、標本抽出の際には、標本ができるだけ母集団の特性を正確に反映するようにするために、さまざまな工夫が求められます。調査を行う際に、不確実性やばらつきを考慮するために、確率や確率分布、確率変数の基礎的な知識が不可欠です。確率の概念を理解することで、標本から得られた結果が母集団全体にどの程度適用できるかを判断する手助けになります。確率分布は、ある現象がどのように発生するか、その可能性を数値的に表現する方法であり、統計的な推定を行う際の基本的な道具の一つです。統計学では、私たちが得られるデータがどのようなばらつきを持っているか、またそのばらつきがどのような意味を持つかを評価するためのさまざまな方法が用意されています。標本から得られたデータを元に、母集団についての結論を導き出すために、統計学は役立つツールを提供します。その一つが「平均」と「標準偏差」です。平均は、標本の中心的な傾向を示す指標であり、標準偏差は、そのデータがどの程度散らばっているかを示す指標です。これらの指標を用いることで、標本データの特徴を把握し、母集団全体について推測することができます。正規分布という概念も、統計学の中で重要な役割を果たします。正規分布は、左右対称で鐘の形をした分布曲線であり、自然界や社会現象における多くのデータがこの分布に従うことが知られています。標本データが正規分布に近い形をしている場合、そのデータから母集団についての推定を行う際に、非常に便利な手法が使用できます。正規分布の特徴は、平均値と標準偏差だけでその形状が決まることです。つまり、これら二つの指標を用いることで、データの全体像を理解することが可能になります。さらに、Zスコアを使えば、異なる分布から得られたデータを比較することができ、観測されたデータがどの程度の確率でその値に達するかを推定することができます。このような手法を用いることで、標本データから得られる誤差の範囲を評価し、母集団全体についての推測をより正確に行うことができるのです。統計学において、特に興味深いのは「仮説検定」という考え方です。仮説検定とは、得られたデータが偶然によるものか、あるいは何らかの実際の効果を示しているかを判断するための手法です。たとえば、二つの異なる標本が同じ母集団から得られたものかどうかを検証する際に、この仮説検定が用いられます。仮説検定の基本的な考え方は、「帰無仮説」と呼ばれるものを立て、それを検証することです。帰無仮説とは、「得られた差は単なる偶然によるものである」という仮定のことです。この仮説が正しいかどうかを検定することで、得られたデータが偶然によるものか、それとも何らかの実際の違いを示しているかを判断します。もし、仮説検定の結果、得られた差が偶然にしては大きすぎると判断される場合、その帰無仮説は棄却され、得られた差は実際の違いを示していると解釈されます。このような検定を行う際、通常は95%の確信度や99%の確信度が使用されます。これは、得られた結果が偶然である可能性が5%未満である、あるいは1%未満であると判断された場合に、その差は実際の違いであると結論づけるということです。これにより、二つの標本が同じ母集団から得られたものであるかどうかを判断できるようになります。しかし、たとえ統計的に有意な差が得られたとしても、それが実際に意味のある差であるかどうかは別問題です。統計的有意性と実際の意味のある違いを混同しないことが重要です。複数の標本の間に有意な差があるかどうかを決定するための手法として、「分散分析」があります。分散分析は、グループ間のばらつきとグループ内のばらつきを比較することで、標本間の差が偶然によるものかどうかを評価します。この手法は、複数のグループを比較する際に非常に有用です。また、質的変数を扱う場合には、カイ二乗検定というノンパラメトリックな手法が用いられます。これは、二つのグループ間の比率に有意な差があるかどうかを検証する際に使用されます。カイ二乗検定では、期待される観測値と実際の観測値との違いを評価し、その違いが偶然によるものかどうかを判断します。質的変数を扱う際には、カイ二乗検定のようなノンパラメトリックな手法が不可欠です。さらに、母集団が正規分布に従っているかどうかが明確でない場合にも、この手法が推奨されます。
関連記事