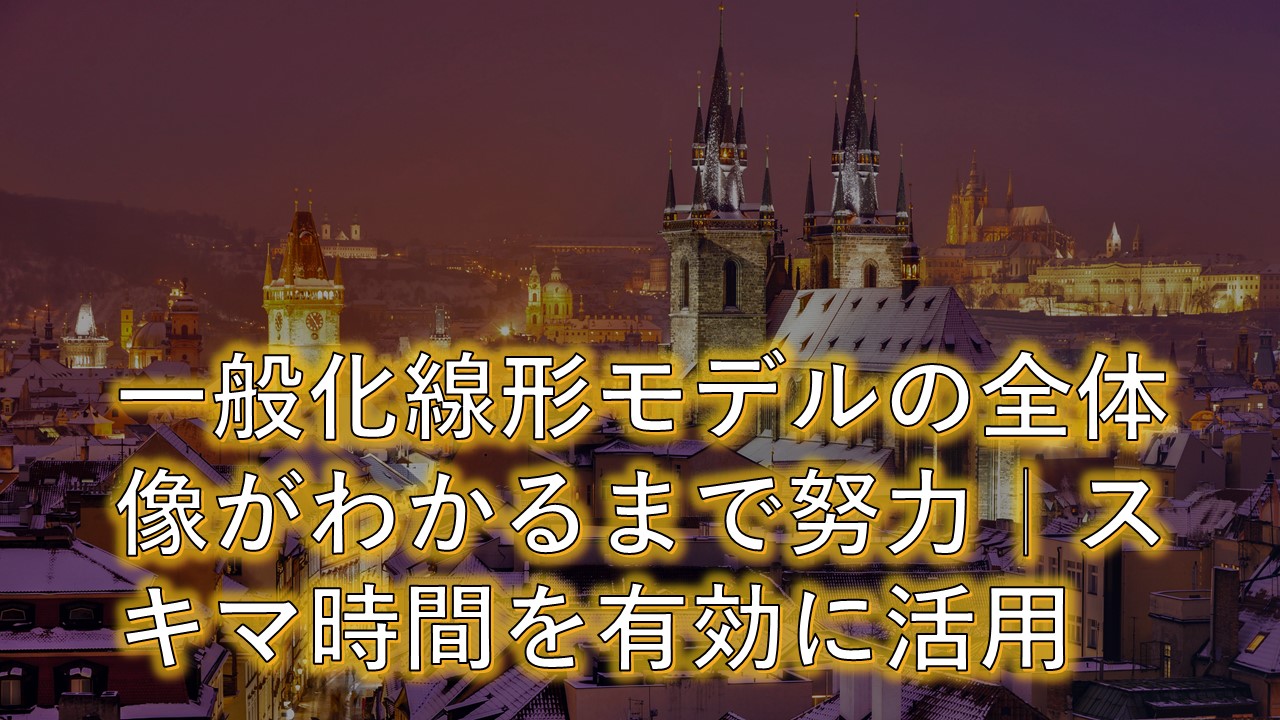スキマ時間で掴む! 統計学の全体像30日プラン【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】
統計学、特に一般化線形モデルの学習では、忙しい日常の中でもスキマ時間を見つけて効果的に活用することが重要です。通勤時間や待ち時間を利用して、統計学の記事を読んだり、オンライン講座のビデオを視聴したりすることで、少しずつでも知識を積み重ねることが可能です。電子書籍やスマートフォンのアプリを使うと、学習資料を手軽に持ち運べ、いつでもどこでも学習できます。毎日少なくとも10分間の学習を心がけることで、断片的な知識から一般化線形モデルの全体像を掴むまでの理解を深めることができるでしょう。
![]() ▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼
チャンネル登録はこちら
目次 スキマ時間で掴む! 統計学の全体像30日プラン【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】
一般化線形モデルの全体像がわかるまで努力する
「統計学を勉強する時間がない」
「平日は夜まで働いていて、土日は休みたいし、勉強の時間などとてもとれない」
と嘆く方は多いかと存じます。
しかし、「時間がない」と言っているだけでは物事は前に進まず、いつまでたっても統計学を身につけることはできません。
ここで、「時間がない」ではなく「どうすれば時間をつくることができるか」という発想に転換しましょう。
そうすることにより、解決のためにいろいろなアイデアが湧いてきます。
私はよく、統計学をマスターするために200時間は勉強しなさい、と言います。
これには根拠があり、統計学は断片的な知識を積んでいる間は、全体像を掴めないという面があります。
例えば、t-検定、分散分析、回帰分析、重回帰分析、ロジスティック回帰分析を、それぞれ20時間ずつ勉強したとします。
これらを個々に勉強している間は、個々のことしかわかりません。
しかし、これら全てを勉強すると、あることがわかります。さて何でしょう。
そう、すなわち「一般化線形モデル」の枠組みです。
一般化線形モデルとは、説明変数を使って目的変数を予測する線形モデルです。
説明変数が名義変数(薬剤群、プラセボ群など)で目的変数が連続変数(血圧、血糖値など)の場合は、群間比較のt検定や分散分析になりますし、
説明変数と目的変数がいずれも連続変数の場合には回帰分析になります。
そして、これらを一通り勉強すると、すべては一般化線形モデルの枠組みで説明できるのだという、いわば「気づき」が得られます。
この気づきを得るまでに、ある程度の時間が必要というのが統計学にはあります。
そのレベルに達すると、理解が飛躍的に深まります。
どうか、このレベルに達するまで、歯をくいしばってでも頑張っていただきたいと思います。
スキマ時間を有効に活用
あなたは、電車に乗っている時、何をしていますか。
寝ている、本を読んでいる、ぼーっとしている、スマホでゲームをしている、など人それぞれかと思います。
しかし考えてみると、電車で通勤している時間というのは、往復で1時間としても、月に20営業日とすると20時間もの長い時間になります。
この時間は有効に使わないと勿体ないです。
電車が空いているときは、PCを出して作業することもあります。
表計算や図作成ではマウス操作が必要ですが、電車の中ではさすがにマウス操作は無理なので、文書作成の作業が中心となります。
電車が混んでいる時は、当然PCを出すことはできませんので、スマホで情報収集します。
ここで大事なのは、電車の中の10分という短い時間でも無駄にしないことです。
なお、バスの中ですが、バスはとても揺れます。
ともすると作業自体が眼によくありませんので、私はバスの中ではぼーっとしていることが多いです。
本を読むということに関しては、PCと違って立ち上げに時間がかからずすぐ読めるというメリットがあります。
難点は重いということです。
文庫本サイズなら問題ありませんが、ちょっと厚めの本だとカバンの中を占有しますし重いのであまりおすすめしません。
電子書籍をおすすめします。
例えば東京から大阪へ移動するのに、あなたは何を利用しますか。
私の場合問答無用で新幹線を利用します。
仮に飛行機の方が早く着くとしても、新幹線を利用します。
なぜなら、新幹線はまとまった時間があるので作業が可能だからです。
マウス操作は難しいですが、文書作成なら十分可能です。
飛行機は作業時間が短いですし、そもそも揺れるので作業には向いていません。
新幹線の切符購入時に窓側を選択すると、コンセントがありますのでPCの電源も確保できます。
PCのバッテリーには限界がありますので、電源は確保したいところです。
電源のない車両もありますので、窓口購入時に電源のある窓側をリクエストすると確実です。
新幹線では、運が悪いと隣や後ろで知り合い同士が座りおしゃべりをするうるさい指定席にあたってしまう場合があります。
話しをするなともいえないですし、運がわるいと思ってあきらめるか、駅員と交渉して席を移動するしかありません。
スキマ時間は必ずしも電車の中だけではありません。
銀行のATMやレストランなどで待っている時間など、探せばいくらでもあります。
もちろんこの場合作業は出来ませんが情報収集は可能です。
スキマ時間を有効に活用するかどうかで、人生そのものが大きく変わります。
まとめ
統計学の学習において、一般化線形モデルの全体像を掴むことは、その分野に深く入り込むために非常に重要です。
そして、多忙な日々の中で「時間がない」という課題に直面しても、スキマ時間を有効活用することで、学習に必要な時間を確保することが可能です。
以下は、一般化線形モデルの学習にスキマ時間を活用するための戦略をまとめたものです。
統計学の基礎を固める
断片的な知識よりも全体像を理解することを目指す: t-検定、分散分析、回帰分析などの基本的な統計手法を個別に学習することも重要ですが、これらがいかに一般化線形モデルの枠組みに組み込まれるかを理解することがキーです。
小分けに学習する
統計学は広範囲に及ぶため、全体を一度に学ぼうとすると圧倒されがちです。スキマ時間を利用して少しずつ、具体的な概念や手法に焦点を当てて学習しましょう。
スキマ時間の活用法
通勤・通学時間の利用: 電車やバスでの移動時間は、統計学に関する記事を読んだり、オンライン講座のビデオを視聴したりするのに適しています。
電子書籍やスマートフォンのアプリを活用すると、重たい本を持ち歩く必要もありません。
待ち時間の活用: ATMでの待ち時間やレストランでの待ち時間など、日常生活で発生する短い待ち時間を活用して、統計学の用語や公式を復習することも有効です。
長距離移動の活用: 新幹線などの長距離移動では、より集中して学習することが可能です。このような時間は、より複雑な統計モデルの学習やプロジェクトに取り組むのに適しています。
効果的な学習ツールの選択
電子書籍やオンラインリソースの利用: 持ち運びが便利で、すぐにアクセスできる電子書籍やオンラインリソースを活用しましょう。
アプリやウェブサービス: 統計学を学ぶためのアプリやウェブサービスを活用することで、どこにいても学習を続けることができます。
毎日の学習時間を設定する: 毎日少なくとも10分間は統計学の学習に費やすようにしましょう。短い時間でも、継続することで大きな進歩を遂げることができます。
ChatGPTに聞いてみた
プロンプト
あなたは最高のデータサイエンティストです。
統計学を学習する上での時間管理について解説してください。
#制約条件:
サルでもわかる平易な日本語で
文字数は300字程度
ChatGPTの回答
統計学を学ぶとき、時間管理はとても大事です。まず、毎日少しずつ勉強することが大切。統計学は少し複雑なので、一度にたくさんのことを覚えようとすると混乱するかもしれません。だから、毎日決まった時間に少しずつ勉強しましょう。次に、勉強する内容を計画的に決めておくこと。統計学の基本から始め、徐々に難しい内容に進むようにしましょう。わからないことがあれば、その都度しっかりと理解するまで時間をかけることが重要です。また、実際にデータを使って分析を行う練習をすることも大切です。理論だけでなく、実践を通じて学ぶことで、より深く理解が進みます。最後に、休憩も大事。集中して勉強できるように、適切に休憩を取りながら、リフレッシュしましょう。このように計画的に学習を進めることで、効率良く統計学をマスターできます。