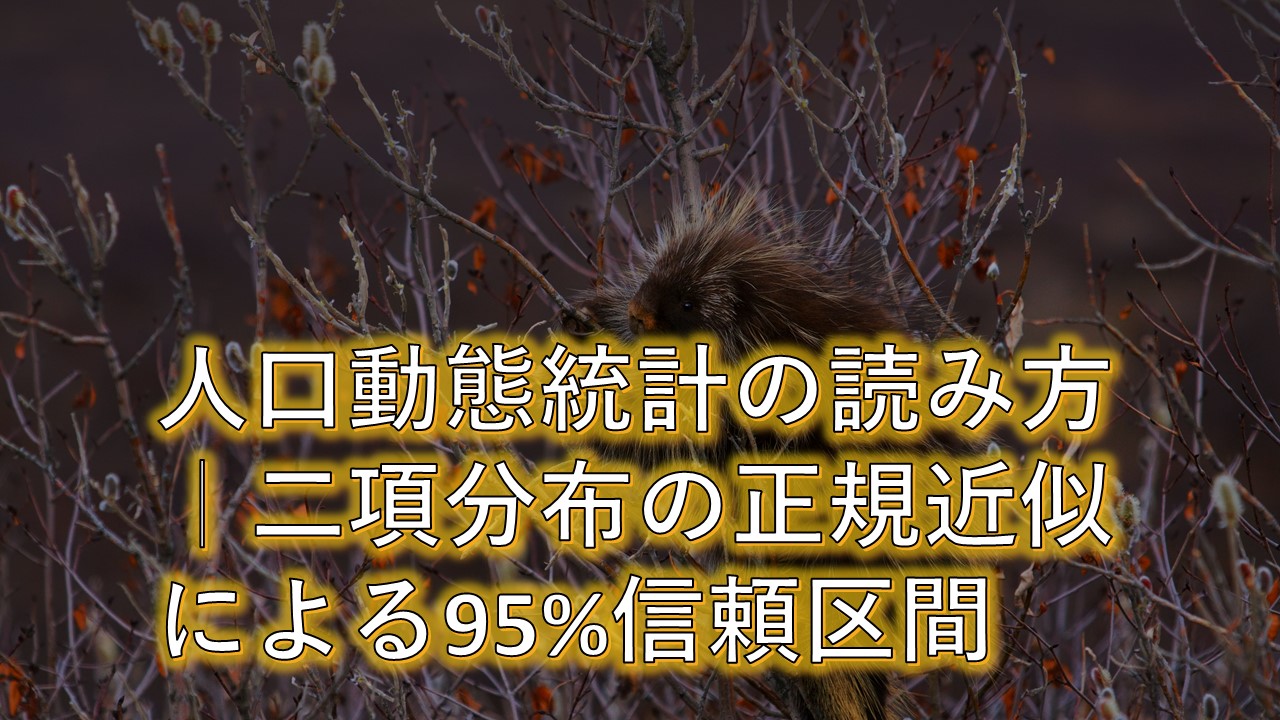肺塞栓症急増!手術後の隠れたリスクを解明【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】
人口動態統計を読む際は、単なる事実を超え、背景や原因を理解することが重要です。例えば、1998年の10年間で肺塞栓症による死亡者数が591人から1655人に増加したことは、人工関節手術などの増加が一因とされています。これらの手術後に血栓が形成され、肺塞栓症を引き起こす可能性があります。三重大学での研究では、肺塞栓症患者の約40%が手術を経験しており、二項分布の正規近似を用いた95%信頼区間に基づくと、手術が原因となる患者は最低でも32%にのぼると示されました。日本では手術後の抗凝固剤使用が欧米ほど一般的ではなく、代わりに下肢圧縮ポンプや弾性ストッキングを使用して予防策を講じています。このように、統計データの背後にある理由を理解することが、知識の深化につながります。
![]() ▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼
チャンネル登録はこちら
人口動態統計の読み方
「肺動脈に血栓」突然死2.8倍と報告されました。
この記事のソースは厚生労働省による人口動態統計ですから、信用できると考えます。
しかし、2.8倍とは、どこのデータで言っているのでしょうか。
1988年から1998年の10年間で、肺塞栓症による死亡者数が591人から1655人に増えています。
つまり、1655÷591=2.8倍とわかります。
肺塞栓症による死亡者数の統計、およびその中で手術の有無に関する調査は、年ごとの横断研究だと考えるのが一般的だと思います。
手術は死亡する前に行っているはずですから、細かく言いますと手術から肺塞栓症になり死亡するという経過は、縦断研究と考えることもできないわけではありません。
それでは、肺塞栓症による死亡者数がなぜ増えたかを説明できますか。
記事にも書いてありますが、「人工関節などの手術の増加」が原因と思われます。
このような手術で起こる血栓(血の塊)が下肢へ移行し、さらに肺の方へ移行すると肺塞栓症になるからです。
こういった背景を知ることが大切です。
単に事実だけを知るのではなく、どうしてそうなったかも合わせて理解しておくことが勉強になるのです。
それを裏づけるデータも示されています。三重大学での肺塞栓症160人のデータです。
カルテから肺塞栓症の患者さんを見つけてきて、肺塞栓症になる前にどのようなことを行っていたのかを調べたものです。
この中の約4割の患者さんが手術をしていたので、肺塞栓症の半分近くが手術起因(手術が原因)と思ったわけです。
ただし、このデータは160例にすぎませんので、その信頼性は低いと思われるでしょう。
二項分布の正規近似による95%信頼区間
統計学の簡単な知識を使うと、
40%±2×√(40×(100−40)/160=40±8=32-48%
の間に真値があると、ほぼ(95%の確率で)いえるのです。
難しいことをいうと、二項分布の正規近似による95%信頼区間を使っています。
つまり、肺塞栓症になった患者さんの中で手術が原因の人は、低く見積もっても32%もいることがわかります。
余談ですが、日本ではまだこのような手術の後にあまり抗凝固剤を用いていませんが、欧米では低分子ヘパリンという抗凝固薬などを標準的に用いているようです。
人工関節などの手術をされた方は知っていると思いますが、日本では下肢圧縮ポンプを付けたり、弾性ストッキングという少しきつめの靴下で下肢の静脈を流れやすくして、静脈血栓塞栓症や肺塞栓症を予防しています。
関連リンク