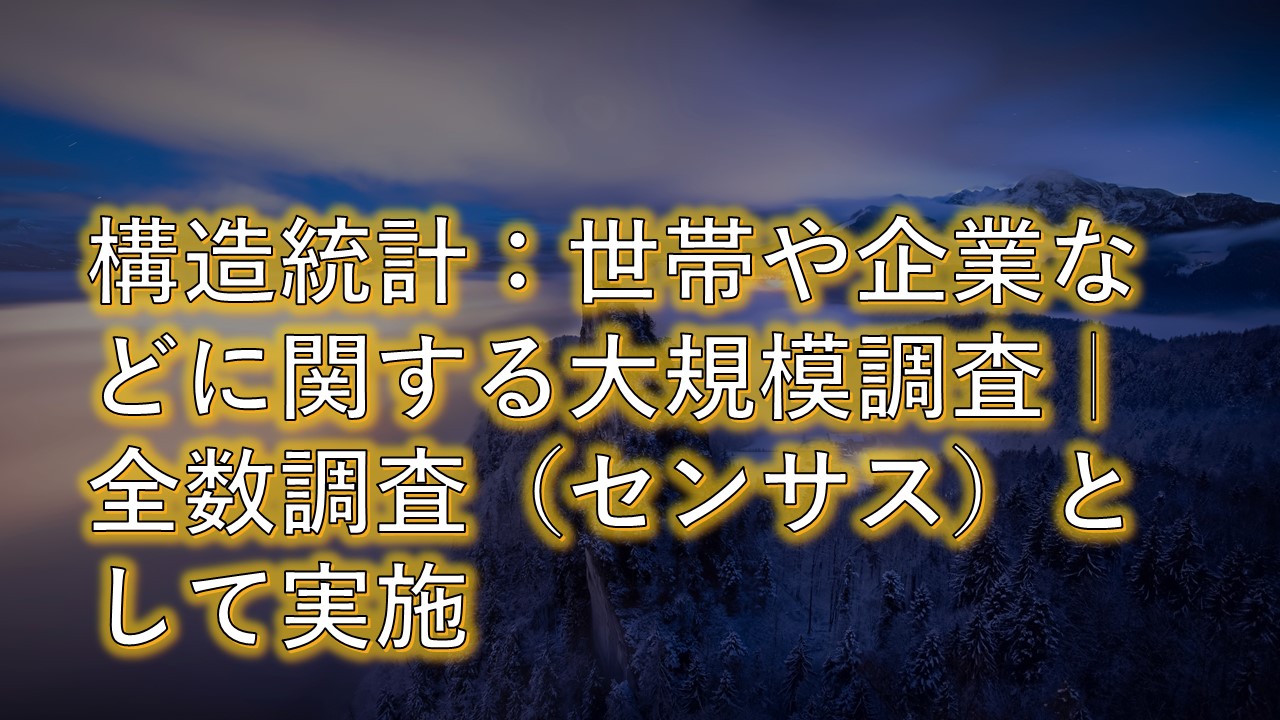全数調査で解き明かす社会の全貌【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】
構造統計は、世帯や企業などに関する網羅的な統計であり、全数調査(センサス)またはそれに準じた方法で実施されます。この調査は、社会や経済の構造を明らかにする主要な情報源であり、3年から5年ごとに行われることが多いです。高額な費用がかかるため、例えば国勢調査のように数百億円を費やして数万人の調査員を動員することもあります。統計調査は、実際に政策を実行する上で必要な情報を提供するため、住民基本台帳のような既存の記録では把握できない詳細なデータを収集する目的で行われます。教育水準、職業、居住地域、婚姻関係などの重要な事項を明らかにし、効率的な標本調査のための正確な名簿を作成することが一つの目的です。
![]() ▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼
チャンネル登録はこちら
目次 全数調査で解き明かす社会の全貌【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】
構造統計:世帯や企業などに関する大規模調査
社会、経済に関する主要な情報源は大規模な構造統計と、時間的な変化を概観する動態統計に区別されます。
構造統計とは、世帯や企業などに関する網羅的な統計であり、全数調査(センサス)あるいはそれに準じるかたちで実施されます。
その費用が大きいため、3年ないし5年に一度の終期で実施されることが多いです。
たとえば、世帯に関する構造統計の代表であります「国勢調査」は5年ごとに実施され、その費用は数百億円という膨大なものです。
2000年の国勢調査では約83万人の調査員が全国の各世帯を調査しましたが、費用の大部分はこれらの非常勤公務員に対する人件費です。
経済社会の構成要因としては、生産の主体としての企業、事業所の調査もあります。
多くの費用をかけて大規模構造統計調査が実施される最も重要な目的として、国全体の構造を明らかにするための資料を作成することがあげられます。
人口や企業数などは改めて統計調査を実施するまでもなく明らかではないかと考える人もいるでしょう。
アメリカのような住民登録制度のない国の場合はともかく、わが国にように識字率が高く、法律を遵守する国では住民基本台帳を利用すれば十分であるという意見を聞くこともあります。
実際、国全体の人口について2000年の結果を比較すると、国勢調査では10月1日の人口が1億2562万人であるのに対して、住民基本台帳では3月31日の人口が1億2618万人と、ほぼ一致しています。
集計の時点に差があることを考えれば、56万人、0.5%の数値の違いは非常に小さいといえるでしょう。
しかし、都道府県別、年齢別、性別に見ると、顕著な違いが出る場合も少なくありません。
同じ2000年の結果によれば、13都府県において人口総数で2万人以上の違いがあります。
また性別、年齢階級別ではその差はさらに大きくなります。たとえば、表1のように京都府の20〜24歳では10%近い違いが生じています。
このようなことから、学校など教育施設の設置や介護対象となる年齢の人口など、現実的な政策を実行する上で必要な情報を得るためには統計調査が必要と認められています。
このことは企業や事業所についても同様であり、法務省に登記されている会社法人数と、実際に税務申告をしている法人数の間には10%程度の違いがあります。
全数調査(センサス)として実施
以上の理由のほか、住民基本台帳などの届出によっては把握できない重要な事項が多数存在します。
たとえば教育水準と職業、居住地域、婚姻関係などを知ることは今後の職業訓練の必要性を判断する上で欠かせない項目ですが、これらは住民票コードなどの管理番号を利用してさまざまな届出を集計したとしても完全とはいえません。
そのことは、婚姻関係とは内縁関係なども含めた実際の状態を把握するものであること、就業状態とは短時間のパート・アルバイトなど雇用保険が適用されないものも含まれることなど、統計調査における基本的な概念を知れば、よく理解されるでしょう。
ところで、いかに正確な数値が求められるとはいえ、費用の点から、全数調査として実施される統計には限りがあります。
そのため、ほとんどの調査においては標本調査が導入されています。そこで説明されるように、少ない費用で効率的な標本調査が実施されるためには正確な名簿が必要です。
構造調査を全数調査として実施する理由のひとつは、調査の結果得られた家計や企業、事業所の名簿を、標本調査を実施するために利用することです。
世帯調査では、勤労者世帯と自営業者世帯の比率や持ち家の比率を利用して適当な調査対象が選ばれます。
同様に、企業調査では業種や規模に関する名簿の情報を利用して標本が選ばれます。
ChatGPTに聞いてみた
プロンプト
あなたは最高のデータサイエンティストです。
全数調査で解き明かす社会の全貌について解説してください。
#制約条件:
ですます調の平易な日本語で
文字数は1000字程度
情報ソースも記述してください。
ChatGPTの回答
全数調査は、ある集団や地域、国などの全ての対象を対象にした調査のことを指します。この方法は、サンプリング調査(一部のみを抽出して調査する方法)と対比されます。全数調査により、より正確で包括的なデータを得ることができ、そのデータを基に社会の様々な側面を深く理解することが可能となります。
社会の全貌を解き明かすためには、多方面からのデータを集める必要があります。例えば、人口統計、経済活動、教育レベル、健康状態、住居状況など、様々なデータが必要となります。全数調査を行うことで、これらのデータを正確に把握し、社会の実情に即した政策立案や、必要なサービスの提供に役立てることができます。
全数調査の一例としては、国勢調査があります。国勢調査は多くの国で定期的に行われ、人口の数、分布、家族構成、教育レベル、就業状況などの情報を収集します。この調査により得られたデータは、国や地域の社会政策、教育、交通、医療などの計画に不可欠なものとなります。
しかし、全数調査には大きな課題もあります。その一つは、膨大なコストと時間がかかることです。全ての対象についてデータを収集し、分析するには、多大な労力と費用が必要となります。また、データの収集と分析の過程で、プライバシーの保護や個人情報の扱いにも細心の注意を払う必要があります。
さらに、全数調査を行うには、高度な技術と専門知識が求められます。データの正確性を保証し、有意義な結果を導き出すためには、統計学的な手法やデータ分析の技術が不可欠です。そのため、専門のデータサイエンティストや調査員がチームを組んで調査を行うことが多いです。
全数調査を通じて社会の全貌を解き明かすことは、私たちが直面している社会問題への理解を深め、より良い解決策を見つけ出すための重要なステップです。データに基づく洞察は、社会の発展と人々の生活の質の向上に直結します。そのため、全数調査の重要性は今後も高まることでしょう。
情報ソースとしては、主に政府や国際機関が実施する調査結果や、学術研究機関による研究報告が参考になります。これらの情報源は、公式のウェブサイトや学術雑誌、報告書などで公開されており、誰もがアクセスできるようになっています。
関連リンク