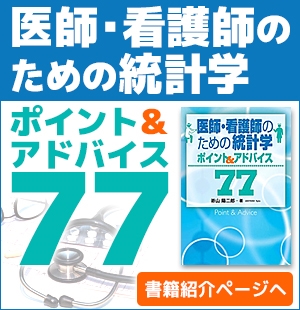分解能で解く実験計画法の交絡構造【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】

分解能は、実験計画法において交絡の程度を示す指標です。一部実施法では、定義対比に並んだ数字の個数が分解能となり、複数の定義対比がある場合は最小の数字の個数を用います。分解能は通常ローマ数字で表記され、例えば「Ⅲ」は数字が3つ、「Ⅳ」は4つのものを指します。①分解能Ⅲ:主効果と2因子交互作用、定数項と3因子交互作用が交絡。②分解能Ⅳ:主効果と3因子交互作用、2因子交互作用同士が交絡。計画を記述する際、分解能を明示するために添え字として表示することがあります。
![]() ▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼
チャンネル登録はこちら
分解能
実験計画法の一部実施法において、交絡の仕方を表す指標です。
一部実施法の定義対比に並んだ数字の個数を指します。
定義対比が複数個ある場合には、それらの定義対比における数字の個数の最小値が分解能となります。
分解能はローマ数字で表す習慣があります。
定義対比の数字の個数が3つのときは分解能Ⅲ、4つのときは分解能Ⅳといいます。
分解能Ⅲの実験では主効果と2因子交互作用、定数項と3因子交互作用とが交絡します。
分解能Ⅳの実験では、主効果と3因子交互作用および2因子交互作用同士が交絡します。
一部実施計画を記述する際、その計画の分解能を明示的に示すため分解能を添え字としてつける場合があります。
分解能(resolution)は、実験計画法における交絡の度合いを示す重要な指標です。
特に、一部実施法(fractional factorial design)**を用いる場合に、どの程度の交互作用(interaction)が混ざり合って解析が困難になるかを理解するために使います。
交絡とは、異なる要因の効果が統計的に区別できなくなる状態のことを指します。
これが起きると、実験結果の解釈が不明確になり、結論の妥当性に影響を与えます。
実験計画では、すべての要因とその交互作用を完全に実施することが理想的ですが、要因が増えると試行回数が指数関数的に増え、時間やコストがかかるため、全ての組み合わせを試すことが困難になります。
このような場合、一部の組み合わせを抽出して行うのが一部実施法です。
一部実施法では、特定の交互作用をまとめて解析するために「定義対比(defining contrast)」という概念を使います。
この定義対比には、実験で採用する要因や交互作用がどのように組み合わさるかが示されています。
各定義対比の中での数字の個数が、実験計画の分解能の決定に関わってきます。
分解能は、各定義対比の中に含まれる数字の個数に依存します。
複数の定義対比がある場合、その中で最も少ない個数が分解能として採用されます。
例えば、ある実験で以下のような定義対比があったとします:
定義対比A: 3つの要因
定義対比B: 4つの要因
この場合、分解能は3つとなり、「分解能Ⅲ」と表現します。分解能は通常、ローマ数字で表され、「Ⅲ」や「Ⅳ」のように記載します。
分解能が異なると、交絡する要因や交互作用の種類も変わります。以下は、代表的な分解能とその特徴です。
分解能Ⅲ(Resolution III)
主効果(main effect)と2因子交互作用が交絡する。
定数項と3因子交互作用も交絡する。
例:ある要因Aの効果と、他の2要因B×Cの交互作用が区別できない状態。
この分解能では、主効果を検出することはできますが、2因子交互作用の影響が紛れてしまうため、2要因間の相互作用を正確に評価するのが難しくなります。
分解能Ⅳ(Resolution IV)
主効果と3因子交互作用が交絡する。
2因子交互作用同士が交絡する。
例:要因Aの効果と、要因B×C×Dの交互作用が重なり合う。
この分解能では、主効果を比較的正確に推定できますが、2つ以上の交互作用の解釈には注意が必要です。
分解能Ⅴ(Resolution V)
2因子交互作用と3因子交互作用が交絡する。
例:要因A×BとC×D×Eの間の交互作用が区別できない。
分解能Ⅴでは、主効果や2因子交互作用をより正確に評価できますが、3因子以上の交互作用の解析は困難になります。
分解能の選定基準と実験目的
実験で使用する分解能は、実験の目的やリソースによって異なります。
分解能Ⅲ:リソースが限られている予備実験などで利用され、主効果の推定が優先されます。
分解能Ⅳ:主効果の検出と、ある程度の交互作用を評価する必要がある場合に使われます。
分解能Ⅴ以上:より複雑な交互作用を解析する必要がある本格的な実験で使用されます。
高い分解能を持つ実験は、試行回数が増え、コストもかかります。そのため、目的に応じて最適な分解能を選択することが重要です。
分解能の選択におけるトレードオフ
分解能が高くなるほど、試行回数が増加し、実験の負担が大きくなります。
一方、分解能が低すぎると、主効果や交互作用の区別が難しくなり、実験結果の解釈が不正確になるリスクが高まります。
このように、リソースの制約と解析の精度の間でバランスを取ることが必要です。
分解能は、実験計画法において交絡の程度を示す重要な概念であり、特に一部実施法では不可欠な指標です。
分解能Ⅲでは、主効果と2因子交互作用が交絡し、分解能Ⅳでは主効果と3因子交互作用が交絡します。
実験計画では、目的に応じて適切な分解能を選ぶことが重要です。
分解能が高いほど詳細な解析が可能になりますが、試行回数が増えるため、計画のリソースと目的を踏まえてバランスを取ることが求められます。
このように、分解能を理解し適切に設定することで、実験計画を効率的かつ効果的に実施できるようになります。
関連記事