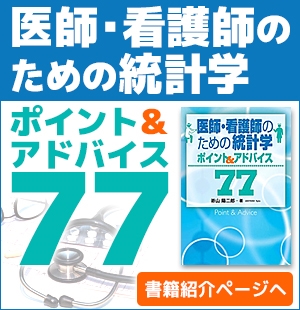データ収集の最適化:タイミングと品質管理の鍵【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】

データ収集では方法と時期を考慮する必要があります。以前は全症例が終了後に一括収集されましたが、この方法ではミスの早期発見や対策が難しく、品質管理が不十分でした。現在はデータを逐次収集し、品質管理や医師へのフィードバックを行う体制へと変わっています。この方法はデータレビューの効率化にも役立ちますが、過剰な収集は避けるべきです。また、データの収集レベルも、目的に応じて最適な情報を選定し、適切に判断することが重要です。
![]() ▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼
チャンネル登録はこちら
データ収集の時期
データの収集に際しては、その方法だけでなく、時期というものも考えておかなければなりません。
ひと昔前は、症例報告書はその症例に対する全ての観察が終了した後に一括して記入されて回収されることが多く、場合によってはその施設での全症例に対する全ての観察が完了した後ということすら珍しいことではありませんでした。
しかしながら、このような方法では既に発生してしまったミスを発見できたとしても手遅れという状態であり、次の症例では同じミスを繰り返さないように適切なモニタリングを行うということは困難でした。
臨床試験に品質管理が求められる以上、このような対応方法で十分な品質管理を行うことができるとは考えられません。
さらに臨床データマネジメント部門にとっても、一度に大量の臨床試験データを確認するということはとても大変なことであり、可能であるならば、ほぼ一定量のデータを継続的にレビューできる方が仕事量の均一化、その臨床試験におけるデータレビューでのノウハウの蓄積という面から考えると非常に意味のあることです。
このため、逐次、臨床試験データを回収し確認できるように工夫をこらし、症例報告書の形態を含めて適切な品質管理を行い得る体制に変化してきています。
また、逐次に臨床試験データが回収できるということは、品質管理ということだけではなく、医師などに定期的に情報をフィードバックすることができるようなサービスが提供できるということも大きなメリットです。
この他にも、ある時点の臨床試験データが次の治療方針を決めるために必須の情報であるという場合には、必要な臨床試験データについて症例報告書への記載をお願いし、症例報告書を回収しておくことにより間違いなく必要な臨床試験データが参照されたはずであるということをあらかじめ確認するという方法が考えられます。
場合によっては、必要な臨床試験データに基づいた判断結果を医師にフィードバックし、正しく次の治療方針が採択されるような指示資料として提供するというように利用することも可能でしょう。
このように、セントラルの都合だけを主張するのではなく、医師などに対しても、臨床検査値の推移図の提供などといった、逐次データ回収によるメリットが実感できるようなサービスを提供することにより、スムーズな協力が得らえるようになるはずであり、皆の協力があってこそ実際の運用が可能になるということを理解しておくべきです。
ただし、むやみと頻回に臨床試験データを回収することが妥当であるというわけでもありません。単に収集と確認の手間を増やしているだけにすぎないことも考えられます。
このため、その臨床試験データがいつ、どのようなタイミングで発生するのかということを理解し、どのような方法と頻度で収集することが望ましいのかということを検討しておく必要があります。
特に中央(セントラル)モニタリングを実施する場合には、実現可能性も含めて適切なタイミングを設定すべきでしょう。
そして、実際に臨床試験データ回収を担当するモニターには、そのタイミングで回収することの意味を十分に理解してもらっておく必要があります。
データ収集のレベル
集計・解析の方針が影響を与える可能性がある臨床試験データ収集のレベルということも検討すべき事項です。
たとえば、併用薬についての情報を収集する場合に具体的な併用薬名を確認したいのか、それともプロトコルで規定されている併用禁止に該当する薬剤が使用されていないことを確認するために薬効軍でのチェックだけが行えればよいのかというようなことです。
前者であれば薬剤名を症例報告書に記載してもらわなければなりませんが、後者の場合には最初から薬剤名ではなく薬効群を症例報告書に記載してもらう方が適切であるかもしれません。
また、薬剤投与状況についても、完全な投与状況を知りたいのか、どの程度のコンプライアンスであるのかを判断したいのかにより収集方法が異なります。
前者であれば、カレンダーに丸をつけるような形態で症例報告書への記載を求める必要がありますが、後者であれば1週間で何割程度の服薬状況であるかをいくつかのカテゴリーで確認できればよいことになります。
また、併用薬を記載する際に、併用理由を記載するか否かということも検討されるべき事項です。
有害事象、合併症、あるいは基礎疾患として何も記載されていないのに併用薬が用いられていることがあります。
併用薬が使用されているということは、本当は何らかの症状があったから使用されたはずであり、併用薬の投与理由を確認しておくことは有害事象や合併症などの記入漏れを防ぐ有効な手段となりえます。
これらのデータ収集のレベルは、収集される臨床試験データが使用される目的に応じて決められるべきことです。
このほかの事例としては、有無の判断というものがあります。
たとえば、アレルギーの有無ということを確認する場合に本質的には「あり」「なし」だけを確認できればよいはずです。
しかしながら、「あり」と記載されている場合に、本当に「あり」と判断してよいのかどうかを保証するために何のアレルギーであるのかを正確に記載してもらう方が間違いがありません。
たとえば、アレルギーの内容が花粉症と記載されているが、プロトコルで花粉症は問題となるアレルギーではないと規定されていたならば、「なし」という判断に変更してもらうというような処置をすべきかもしれないのです。
このようなことも、どのようなレベルまでデータを収集するかによって対応が変わる一例です。
データ収集においては、その方法だけでなく、収集する時期も非常に重要な要素として考慮されなければなりません。臨床試験や他の研究におけるデータ収集のタイミングは、データの正確性や信頼性、さらには研究全体の効率性に大きく影響を与えるためです。ひと昔前では、症例報告書(CRF: Case Report Form)は、その症例に対する全ての観察が終了した後に一括して記入され、施設全体での全症例に対する全ての観察が終了した後に回収されることが一般的でした。これは、当時の技術的制約や運用上の慣行に起因するものであり、効率的にデータをまとめて処理できるというメリットがありました。しかし、この一括処理方式には大きな欠点も存在しました。例えば、もしデータの記載ミスや欠陥があったとしても、それが発覚するのは全てのデータが集められた後になります。そのため、既に発生してしまったミスを見つけたとしても、その時点では修正が困難であり、次の症例やデータ収集段階で同じミスを繰り返さないようにモニタリングを行うことも難しかったのです。このような手遅れの状態では、データの品質を確保することができず、臨床試験や研究全体の信頼性に悪影響を及ぼす可能性があります。臨床試験においては、品質管理が非常に重要視されており、データの精度や完全性を維持するためには適切なモニタリングが不可欠です。従って、一括収集方式は次第に見直され、データの逐次回収というアプローチへと移行していきました。逐次回収方式では、データが収集されるたびにその都度モニタリングが行われ、早期に問題を発見し修正することが可能になります。これにより、次の症例や次の段階での同様のミスを防ぎ、全体のデータ品質を向上させることができます。また、臨床データマネジメント部門にとっても、一度に大量のデータを確認するよりも、一定量のデータを継続的にレビューする方が作業の負担を均等にしやすく、データのレビューに関するノウハウも蓄積しやすいという利点があります。これにより、作業の効率性が向上し、データの信頼性も高まるというわけです。さらに、逐次データを収集することで、品質管理だけでなく、医師や研究者に対して定期的なフィードバックを提供することも可能になります。臨床試験においては、リアルタイムでのフィードバックが次の治療方針を決定する際に非常に有用であり、データの迅速な回収と分析が必要な場合があります。例えば、ある時点のデータが次の治療決定に必須の情報である場合、そのデータを迅速に回収し、適切なフィードバックを行うことができる体制が求められます。これにより、臨床試験の結果を元にした正確な判断が下され、適切な治療方針が採択されることが期待されます。もちろん、データを頻繁に回収することが必ずしも良い結果をもたらすとは限りません。過度なデータ回収は、作業の手間を増やし、臨床試験の進行を遅らせる可能性があります。したがって、収集するデータのタイミングと頻度は、臨床試験の目的や進行状況に応じて慎重に計画されるべきです。中央(セントラル)モニタリングが行われる場合、データの収集時期や方法についても実現可能性を十分に考慮し、適切なタイミングを設定する必要があります。さらに、実際にデータを回収する担当者であるモニターには、そのタイミングでデータを回収する意味や重要性を十分に理解させ、適切なモニタリングを行わせることが求められます。また、データ収集の際には、集計や解析の方針が臨床試験データの収集レベルに影響を与える可能性があるため、どのレベルでデータを収集するかを検討することも重要です。例えば、併用薬の情報を収集する場合、具体的な併用薬名を確認する必要があるのか、またはプロトコルで規定された併用禁止薬が使用されていないことを確認するために薬効群だけのチェックで十分なのか、という判断が求められます。前者であれば、症例報告書に具体的な薬剤名を記載してもらう必要がありますが、後者であれば薬剤名ではなく、薬効群の記載で済むこともあります。このように、収集するデータの具体的なレベルは、収集されたデータがどのように使用されるかに応じて決められるべきです。また、薬剤投与状況についても、完全な投与状況を知りたい場合と、一定のコンプライアンスを判断する場合では、収集方法が異なります。前者では、詳細な記録が求められ、例えばカレンダーに丸をつける形式での報告が必要ですが、後者の場合は、一定期間での服薬状況をいくつかのカテゴリーに分けて確認するだけで十分かもしれません。さらに、併用薬を記載する際に、その併用理由を記載するかどうかも検討すべき事項です。併用薬が使用されているという事実は、何らかの症状があったからこそ投与された可能性が高く、その理由を確認することで、有害事象や合併症の記入漏れを防ぐ手段となり得ます。このように、データ収集のレベルや詳細さは、試験の目的やデータの利用方法に応じて適切に設定される必要があります。また、アレルギーの有無を確認する際にも同様の考慮が必要です。「あり」「なし」だけの情報が必要な場合もありますが、「あり」とされた場合、その内容を正確に記載してもらうことで、誤った判断を防ぐことができます。例えば、アレルギーの内容が花粉症であり、プロトコル上では問題となるアレルギーではない場合、「なし」として再評価されるべきかもしれません。このように、データ収集の方法やレベルは、試験の目的やデータの利用方針に従って柔軟に対応されるべきです。データ収集の時期や方法については、臨床試験全体の進行に対する影響を考慮しながら、適切なバランスを保つことが求められます。また、モニタリング担当者やデータマネジメント部門との連携を密にし、データの品質を確保しつつ効率的な運用を実現することが、臨床試験や研究の成功につながるのです。このような視点から、データ収集のタイミングやレベルは、単に収集作業の負担を減らすためのものではなく、試験全体の成功に向けての重要な要素であることを理解し、慎重に検討する必要があります。
関連記事