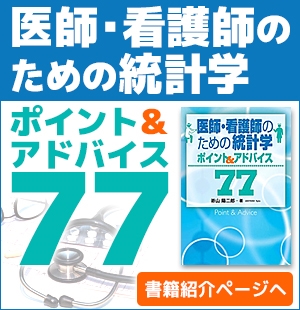臨床試験での過誤と検出力:信頼性向上の鍵【東京情報大学・嵜山陽二郎博士のAIデータサイエンス講座】

臨床試験の仮説検定では、治療効果の同一性を仮定する「藁人形仮説」を設定し、確率論に基づいて棄却の判断を行います。第一種の過誤(α)は、帰無仮説が正しいのに誤って棄却する確率であり、多くの場合、有意水準0.05を採用しますが、多重比較を行う場合は実質的な過誤率が増加します。臨床医は、検定回数と多重比較を考慮する必要があります。また、第二種の過誤(β)は、真の差があるのに帰無仮説を誤って受け入れる確率であり、検出力(1−β)に影響を与える要因には、観察結果の差と主要評価項目の数が含まれます。臨床試験の設計では、十分な検出力(最低80%、望ましくは90%)を確保し、誤った結論を避けるために適切なサンプルサイズを用意することが重要です。観察研究でも、臨床的に重要な差を評価し、結果の信頼性を高めるために検出力を考慮するべきです。
![]() ▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼
チャンネル登録はこちら
統計的考察:第一種の過誤と多重比較
臨床試験の仮説検定は,比較する2つの治療の効果は同一であるという「藁人形論法(straw-man argument)」を設定すると考えることができる.
統計的検定の目標は,確率論に基づいて,この「藁人形仮説(straw man hypothesis)」が許容されるか棄却されるかどうか決めることである.
第一種の過誤(type l error)あるいはαは,帰無仮説(null hypothesis)が正しいときに,誤って棄却してしまう確率である.
臨床医は,(まるでp値が確率の唯一の評価基準であるかのように)シンプルで二者択一の思考様式で訓練されてきているため,第一種の過誤は,一般的に有意水準0.05を用いる.
しかし,同様の質問が繰り返されるとき,すなわち試験内で複数のサブ集団が評価されるとき,「名目上の」0.05未満のp値は,実質的に増加する。
p値の意味を評価するとき,臨床医は有意差検定の数および試験実施者が実施した多重比較に応じたp値に基づいた重要性に留意すべきである.
第二種の過誤とサンプルサイズ
第二種の過誤(type II error)あるいはβは,真に結果に差があるときに,帰無仮説(治療効果に差がない)を誤って許容する確率である.
試験の検出力(1−β)は,一般的に.試験の特質に関心を向けるために使われるp値は帰無仮説を適切に棄却する確率である.
この確率は, (1)治療問に観察される結果の差と(2)主要評価項目の数に,大きく依存している.
検出力について考えるときの一般的な誤りは,患者数が検出力を決定するということであるが,検出力を決定するのはむしろ評価項目の数である.
主要評価項目が測定される精度は,試験の検出力に影響する.
高精度で測定できる評価項目は,より少ない患者で十分である.
この例として.セスタミビ(sestamibi)によって推定される心筋梗塞の大きさがある.
再灌流前のリスクがある領域と,その後の最終的な梗塞の大きさを測定して梗塞の修復を評価することにより,評価項目のばらつきを大きく減少することができる。
しかし,よくあることであるが,より精度の高い測定結果を得ることがより難しく.試験を実施できる施設を見つけることが大変難しくなる.
多くの場合.試験を完了するのに必要な時間は,必要な患者数と同様に重要となる,
行動療法または精神医学の試験では,質問票を開発して使用する際に,同様の議論が,一般的に用いられる詳細な品質管理における主要なきっかけの1つとなる.
生理学的な評価項目を用いる試験では.一般的に,連続値を用いることで差についての検出力を上昇させる.
再狭窄試験では,径狭窄(diameter stenosis)の50%未満の減少を検出ために必要な患者数は,径狭窄の平均値または中央値,あるいは最小内腔径の差を検出するために必要な患者数より大きくなる.
1978年のNew England Journal of Medicineのレビューによると,71の失敗した試験のうち67試験で大きな第二種の過誤があり(25%の治療効果を逃す10%超える可能性). 71試験のうち50試験は50%の治療効果を見落とす10%を超える可能性があった.
残念ながら.それ以来状況はあまり改善していない.
十分な検出力がなく試験が失敗に終わることの最も一般的な理由は.プロジェクトに対する不十分な投資と一部の研究者の熱意がないことである.
臨床試験を実施する際には,少なくとも80%の検出力(90%の検出力がより好ましいが)を保持していることが極めて理想的である.
真の差を検出する確率がほとんどない試験により,期待できるアイデアや治療を捨ててしまうことは,明らかに残念な状況である.
理解することが最も難しい概念の1つに,真の差についての検出力が小さい試験では,より良い治療における有意な差を示す確率が制限されてしまうだけでなく,症例数が少ないことによるばらつきにより観察される治療効果の方向が十分に予測できないことがあげられる.
もし小規模の試験で.観察される効果が誤った方向になる場合,その治療は期待できないが,一方で.もし観察された効果が期待できる方向にあるけれど,p値は有意ではない場合,有意でない理由は,サンプルサイズが不十分であることである.
十分な規模の臨床試験をデザインして実施することにより,これらの問題を避けることができる.
観察的な比較は,少なすぎる患者を組み入れるランダム化試験と同じくらい起こり得る.
しかしながら,観察試験はめったに検出力計算を含まない.
ランダム化試験において一般的に使われているものと同形式の計算が. 0.05より大きいp直として観察された効果をみるために使うことができる.
最小限の臨床的に重要な差を議論し,もし差が存在するのであれば,その差を見つける確率の評価を読者に提供することにより、観察研究の実施者は,その研究をより鋭い視点でとらえることができる.
臨床試験における統計的考察は、治療の有効性や安全性を判断するための重要な基盤であり、仮説検定が中心的な役割を果たします。仮説検定は、2つの治療の効果が同一であると仮定する「藁人形仮説(straw-man hypothesis)」に基づき、この仮説が受け入れられるか、棄却されるかを統計的に判断します。このような仮説検定の基本概念は、多くの医療分野で一般的に受け入れられ、特に第一種過誤(type I error)と第二種過誤(type II error)の管理が重視されています。第一種過誤とは、帰無仮説が正しい場合にこれを誤って棄却してしまう確率を指し、通常αとして示されます。例えば、αが0.05と設定されている場合、帰無仮説が真であっても5%の確率でこれを棄却してしまうことを意味します。多くの臨床試験では、第一種過誤を最小限に抑えるために、有意水準0.05を基準としていますが、この有意水準が絶対的な基準とされることで、医療現場ではp値のみを重視する二者択一の思考様式が定着しがちです。しかし、臨床試験において同じ仮説を複数の異なるサブグループで検定する場合や多重比較を行う場合には、実質的な過誤率が増加することが指摘されています。たとえば、試験内で複数のサブ集団を評価する際に「名目上の」0.05未満のp値が出たとしても、実質的にはそのp値が示す確率的な意味は異なり、正確な有意性の評価を困難にする要因となります。したがって、臨床医や研究者は、得られたp値が多重比較や複数の仮説検定を考慮したものであるかを慎重に評価する必要があります。多重比較が影響を及ぼすケースでは、ボンフェローニ補正やホルム法などの補正手法を用いて、有意水準を調整し、実質的な第一種過誤率を管理することが推奨されます。第二種過誤(type II error)についても理解が重要です。第二種過誤とは、真に結果に差があるにもかかわらず、帰無仮説を誤って受け入れる確率を指し、βとして表されます。検出力(1−β)は、帰無仮説を正しく棄却する確率であり、一般的には試験の特性を評価する上での指標となります。検出力は通常80%以上とされ、臨床試験の信頼性を高めるためには90%の検出力が望ましいとされています。この検出力は、観察される治療効果の差や主要評価項目の数に依存し、サンプルサイズが小さい場合、検出力が低下する可能性が高くなります。検出力が不足する試験は、真の治療効果を示す可能性が低いため、治療の有効性を過小評価し、潜在的に有効な治療を見逃すリスクが生じます。特に、患者数が検出力を決定する要因であると誤解されることがありますが、実際には評価項目の精度やその数も重要な要素です。たとえば、高精度で測定可能な評価項目がある場合、比較的少ない患者数でも十分な検出力を得ることが可能です。心筋梗塞の評価においては、セスタミビを用いて梗塞の大きさやリスク領域を評価することが例として挙げられます。このような精度の高い測定法を用いることで、評価項目のばらつきを抑制し、必要な患者数を減らすことが可能です。しかし、精度の高い測定は実施が困難であり、高度な設備や技術が必要とされることも少なくありません。試験の実施施設が限られている場合、試験の完了までに必要な時間が長くなることが一般的です。特に行動療法や精神医学の試験では、質問票などのツールの開発と管理が重要な課題であり、これが精度や検出力に影響を与える要因となります。生理学的評価項目を用いる試験では、連続変数の使用が一般的であり、これにより検出力を高めることが可能です。再狭窄試験においても、径狭窄の平均値や中央値、あるいは最小内腔径の差を検出するために必要な患者数を減少させることができます。しかし、臨床試験が失敗する要因のひとつは、プロジェクトに対する不十分な投資や一部の研究者の熱意の欠如によるもので、検出力が十分でない試験が実施されることが多くの問題を引き起こしています。1978年に発表されたNew England Journal of Medicineのレビューでは、71の失敗した臨床試験のうち67試験が第二種過誤により治療効果を見逃しており、その後も状況は大きく改善していないと報告されています。臨床試験の設計段階で、少なくとも80%以上の検出力を確保することが理想的であり、期待される効果が検出されない試験によって有望な治療法が無駄にされることを防ぐことができます。小規模な試験では、観察される治療効果の方向がばらつきにより予測困難であり、真の差を示す確率が低くなります。さらに、観察された効果が期待とは逆方向になる場合、その治療は無効と判断されがちですが、もしp値が有意でない場合、その理由が単にサンプルサイズの不足である可能性もあります。適切なサンプルサイズと検出力を確保することで、こうした誤解を避け、正確な治療効果の評価が可能となります。また、観察試験とランダム化試験は異なる特性を持ちますが、観察試験でも検出力を考慮し、臨床的に重要な差を評価することが重要です。観察研究においても、最小限の臨床的に意味のある差を見つける確率を読者に提示することで、研究結果の解釈が容易になります。観察試験では通常、ランダム化試験ほど厳密な検出力計算が行われませんが、これにより効果の真の大きさに関する信頼性が損なわれる可能性があります。ランダム化試験では、通常0.05未満のp値を目指して効果を評価するため、観察された効果を有意に示すための検出力の評価が欠かせません。さらに、臨床試験においては、真の差を適切に検出できる試験を設計することが重要であり、無効な治療を有効と誤解するリスクを避けるための戦略を組み込む必要があります。
関連記事